【小学校】算数の単位の覚え方|スムーズに覚えるための学習法

小学生が算数でつまずきやすいのが3年生頃。
この時期になると、長さ・重さ・面積といったさまざまな「単位」が登場します。
急に覚えることが増えるうえに、日常ではあまり使わない単位もあるため、戸惑ってしまう子も少なくありません。
そこでこの記事では、小学校で習う5つの単位をスムーズに覚えるための学習法をご紹介します。
小学校で習う単位
小学校で習う単位は長さ・重さ・面積・体積・容積の5つです。
単位の読み方や関係、身近なイメージを単位ごとに整理し、一覧表にしました。
学習の際に参考にして下さい。
長さの単位(mm, cm, m, km)の覚え方
長さの単位は、m(メートル)を基準にして考えるのがポイントです。
単位の前につくアルファベット(m・c・kなど)には、それぞれ意味があり、これを理解することで覚えやすくなります。
| 単位 | 読み方 | 関係 | イメージ例 |
| mm | ミリメートル | 1m=1000mm(1mm=1/1000m) | 定規の一番小さい目盛/鉛筆の芯の太さ |
| cm | センチメートル | 1m=100cm(1cm=1/100m) | 人差し指の先の幅/ノートのマス目 |
| m | メートル | 基準の単位 | 身長/新聞紙を広げた対角線の長さ |
| km | キロメートル | 1km=1000m(km=1000倍) | マラソン/学校から家までの距離 |
▶︎ 覚え方のコツ
✓ アルファベットの意味を理解する
単位の頭文字には、それぞれ大きさの目安があります。
- m(ミリ)=1000分の1
- c(センチ)=100分の1
- k(キロ)=1000倍
「m(メートル)」を基準にして、小さい方・大きい方を整理しておくと覚えやすくなります。
✓ 測る・比べる・動いて覚える!体験で単位感覚を育てよう
定規やメジャーで身の回りのものを測ったり、実際に歩いて距離を感じたりすることで、単位の“量感”がしっかり身についていきます。
- mm・cm:ノートの幅、鉛筆の太さなどを定規で測ってみる
- m・km:家から公園までの距離を歩いて体感、「1kmってどれくらい?」を実感
- 1cm=人差し指の幅/1m=ドアの高さ/1km=徒歩やマラソンの距離感など、身近なもので置き換える
重さの単位(g, kg, t)の覚え方
重さの単位は、g(グラム)を基準に1000倍ずつ増えたり減ったりするしくみになっています。
それぞれの単位の意味や大きさの感覚をつかんでおくことで、丸暗記しなくても、自然と理解できるようになっていきます。
| 単位 | 読み方 | 関係 | イメージ例 |
| mg | ミリグラム | 1000mg=1g(1mg=1/1000g) | 錠剤1粒/スパイスのひとつまみ程度 |
| g | グラム | 基準の単位 | 消しゴム1個=約20g/1円玉=1g |
| kg | キログラム | 1000g=1kg | 1Lのペットボトル1本で1kg |
| t | トン | 1000kg=1t(=1000000g) | 自動車/アジアゾウの子ども |
▶︎ 覚え方のコツ
✓ アルファベットの意味で整理すると分かりやすい
- m(ミリ)=1000分の1
- k(キロ)=1000倍
- t(トン)=kの1000倍
グラム(g)を基準に考えると、単位の関係がスッと整理できます。
✓ 身近なものと体験で重さの感覚をつかむ
重さは数字だけでなく、実際に見たり触ったりすることで理解しやすくなります。
- 1mg:塩ひとつまみくらい
- 1g:1円玉くらいの重さ
- 1kg:1Lのペットボトル1本分
- 1t:2Lペットボトル500本分!大きな車や機械の世界で使用
スケールで100gを量ったり、買い物中に食品のgやkgを意識したりすることで、重さの単位が自然と身についていきます。
かさの単位(mL, dL, L)の覚え方
かさの単位はジュースや水、調味料など毎日の生活でよく使われるものばかり。
「1000mL=1L」などの関係を、身近な例でイメージできると、覚えやすくなります。
ペットボトルや計量カップなどを使って、実際に量を見てみるのがおすすめです。
| 単位 | 読み方 | 関係 | イメージ例 |
| mL | ミリリットル | 1000mL=1L | 飲み物のパック(500mLなど) |
| dL | デシリットル | 10dL=1L | 計量カップによく出てくる単位 |
| L | リットル | 基本の単位 | 牛乳パック1本=1L |
▶︎ 覚え方のコツ
✓「1L=1000mL」は“ゼロの数”で覚える
1Lのあとに「0を3つ」で1000mL、0の数で倍数を見分けると整理しやすくなります。
✓dL(デシリットル)を“10の仲間”として意識する
d(デシ)は10分の1や10倍の単位によく出てくるので、「d=10の世界」と覚えるとスムーズ。
✓料理やレシピを使って自然に覚える
「このカップで300mL、じゃあ1Lは?」など、家で使う調味料や飲み物で会話を重ねると、日常に単位が定着しやすくなります。
時間の単位(秒、分、時間、日)の覚え方
時間は日常生活の中でとても身近ですが、60進法という特殊なルールでつながっているため、他の単位よりも混乱しやすい単元です。
まずは、単位どうしの関係とイメージをしっかり押さえておきましょう。
| 単位 | 読み方 | 関係 | イメージ例 |
| 秒 | びょう | 基本の単位 | ストップウォッチ1周/「いーち、にー、さーん」の感覚 |
| 分 | ふん・ぷん | 60秒=1分 | アニメ1話30分/カップラーメンの待ち時間3分 |
| 時間 | じかん | 60分=1時間 | 学校6時間/映画2時間など |
| 日 | にち | 24時間=1日 | カレンダー1日分/朝〜夜の流れ |
▶︎ 覚え方のコツ
✓ 「60」という特別ルールを体感で覚える
時間だけは「60秒で1分」「60分で1時間」という特別な仕組み。
アナログ時計を使って、針の動きや数字の配置を目で見て覚えるのが効果的です。
✓ 時計を使った会話で、自然に換算力をつける
「あと10分で出発」「今から90分後は何時?」など、日常の会話に時計を取り入れることで、時間の単位や計算への苦手意識が減っていきます。
✓ 読み方と単位の変換は段階的に慣らす
短針・長針だけを見る→5とびで数える→午前・午後を区別する…と、読み方のステップを分けて覚えると混乱しにくくなります。
「1.5時間=90分」などの言い換えも、実際にスケジュールなどで見せて慣れさせましょう。
単位換算をスムーズにするコツ

単位換算は、慣れるまでは戸惑いやすい部分ですが、いくつかの工夫をするだけでずっと分かりやすくなります。
ここでは、単位換算をスムーズに行うための3つのコツをご紹介します。
図や表で視覚化する
単位の関係を「頭の中で考える」のは複雑で、覚えるのが大変です。
おすすめなのが、単位の一覧表を壁などに貼って、自然に目に入るようにすること。
- 長さ、重さ、かさ、時間など、一覧になった表を作成する
- トイレやお風呂、勉強机の近くなど通るたびに目にする場所に貼る
インターネットで「単位換算 一覧表」などと検索すると、無料でダウンロードできるものも多くあります。
暗記が苦手なお子さんにおすすめの方法です。
具体例を使って勉強する
単位は、見たり聞いたりするだけではなかなかイメージしにくいもの。
そんなときは、身近な具体例を通じて覚えるのが効果的です。
- 料理で量ってみる
「100gってどのくらい?」「300mLはコップ何杯分?」など、キッチンスケールや計量カップを使って実際に量ってみると、“g”や“mL”の感覚が自然と身についていきます。 - 身の回りを測ってみる
「この本は何cm?」「1mってどれくらい?」など、定規やメジャーでいろいろな物を測ることで、長さの単位も実感しやすくなります。
実体験を通して「cmってこのくらい」「1Lってこの大きさ」と感覚的に理解できると、文章題や換算の問題にも自信が持てるようになります。
練習問題で反復学習を行う
単位の換算は、1度で完璧に覚えられるものではありません。
特に、慣れないうちは「あれ? 何倍だったっけ?」と迷うのが自然です。
だからこそ、くり返し練習することがとても大切。
- まずは「1000g=◯kg」などの基本的な変換から
- 次に「300cm=◯m」「2.5L=◯mL」など、少し応用を
- 最終的には「答えをLで書こう」などの文章題で単位の切り替えに慣れていく
1日数問でもOK。くり返すことで、だんだんと変換が自然にできるようになります。
単位を覚える必要性
単位の学習は難しく感じるかもしれませんが、様々なケースで役に立ちます。
どんなときに単位が必要になるのか、具体的に見ていきましょう。
単位を換算した計算が可能になる
単位の仕組みを知っていれば、計算はぐっと簡単になります。
例えば「500mLのジュースを3本。全部で何L?」という問題も、1500mL=1.5L とスムーズに計算できるようになります。
逆に、「1000g=1kg」や「1.5L=1500mL」などの変換があやふやだと、途中で混乱したり、単位のまちがいでミスをしてしまうことも。
単位をしっかり理解しておけば、数字に強くなって、算数の問題にも自信をもって取り組めるようになりますよ。
日常生活で活用できる
単位は勉強だけのものではなく、毎日の生活の中でも大活躍しています。
例えば、スーパーでお肉を買うとき。「100gあたり○○円」の表示を見て、どれくらい買うか考えたり、料理で「水300mL」とレシピに書いてあったり。
他にも、「あと15分で家を出るよ」と声をかけたり、知らず知らずのうちに単位を使っています。
こうした日常の会話や行動の中で単位の感覚が身についていると、数字にも強くなり、先を見通す力も育っていきます。
単位を分かっておけば、“生活力”も伸びていくのです。
算数以外の強化でも必要になる
単位を理解しておくと、算数以外の教科もスムーズに学べるようになります。
理科では「水を300mL量る」「重さをgやkgで比べる」など、実験で頻繁に登場しますし、社会では「1cm=1km」の縮尺や「15度で1時間」の時差計算などでも使われます。
中学校になると、理科の公式に「Pa=N/m²」などの単位が組み込まれ、さらに複雑に。
そのため、学年が上がるにつれて苦手分野が増えてしまう原因の一つが、「単位の理解不足」なのです。
小学生のうちから単位に慣れておくことが、他の教科の理解や将来の学びにもつながっていきます。
算数の単位、なぜつまずきやすいの?
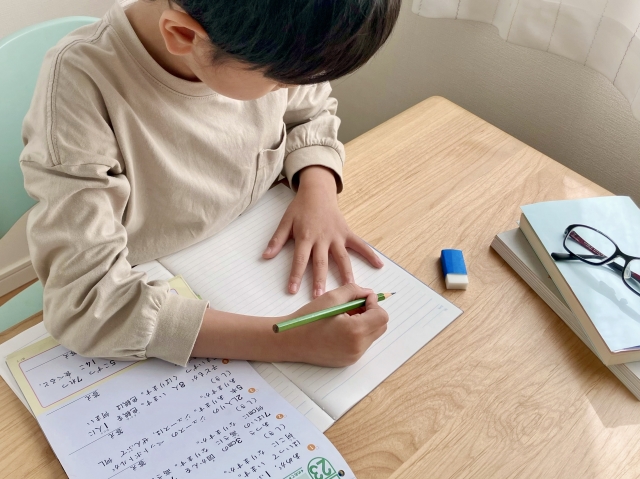
「単位のところになると、急にわからなくなる…」、そんな声をよく聞きます。
ではなぜ、算数の単位は子どもがつまずきやすいのでしょうか?
ここでは主な理由を3つご紹介します。
計算力不足
単位換算には「×10」や「÷1000」などの計算が必要ですが、単位を学び始める小学3年生ごろは、まだ九九や筆算に不安がある子も多く、途中でつまずいてしまうことがあります。
例えば「1200gは何kg?」という問題も、1000で割る計算ができなければ答えが出せません。
単位の意味はわかっていても、計算がスムーズにできないせいで苦手に感じてしまうこともあるのです。
暗記のみで覚えようとしている
「1km=1000m」「1L=1000mL」など、単位は数が多く、全部覚えるのが大変に感じることも。
意味を理解せず丸暗記しようとすると、すぐに忘れたり混乱したりしがちです。
でも、実は単位には「しくみ」があります。
例えば「k(キロ)」は1000倍、「c(センチ)」は100分の1。
こうした接頭語の意味を知っておくと覚えやすくなります。
語呂合わせを使うのも効果的。
「キハダマグロよどこまでも」→ キ(k) ハ(h) ダ(da) マグロ(m/g/L) よど(d) こ(c) ま(m)
こんなふうに楽しみながら覚える工夫をすると、自然と身についていきます。
まとめ
単位のつまずきは、算数が苦手になるきっかけにもなりやすいポイントです。
でも、生活の中で実際に使ったり、親子の会話に取り入れたりすることで、自然と理解が深まっていきます。
少しずつでも大丈夫。
毎日の関わりが、子どもの「わかる!」につながっていきます。
関連するコラム
習い事を検索
-
- (428件)
-
-
-
-
-
-









