九九マスターへの近道!子どもが楽しく取り組める覚え方

小学2年生になると出てくる「九九」。
これからの学習でも非常に重要になってきますし、日常生活で使う場面も多い単元です。
必ず覚えておきたい九九ですが、「むずかしい」「全部おぼえるのは大変…」と苦手意識を持ってしまう子どもも少なくありません。
九九は丸暗記しようとすると難しく感じますが、覚え方を工夫することで苦手意識を軽減することができます。
今回は、九九の意味をしっかり理解しながら、楽しく覚えていけるコツをご紹介します。
掛け算九九が覚えにくい原因
九九が覚えにくく感じるのには、ちゃんと理由があります。
その理由を知ることで、子どもに合ったサポートのヒントが見えてくるはずです。
ここでは、代表的ないくつかの理由を紹介いたします。
暗記量が多い
九九は、子どもにとって初めての“本格的な暗記”と言えるかもしれません。
1の段から9の段まで合わせて81の組み合わせを覚える必要があり、初めて九九表を見たときに「こんなにあるの…!?」と圧倒されてしまう子も多いです。
暗記が得意な子でさえ、量の多さに戸惑いやすく、最初から自信を失ってしまう子どももいます。
たとえば、「3×7?…えっと、なんだっけ?」と一つひとつ確認しながら覚えていくうちに、他の段がごちゃごちゃになってしまうことも。
はじめから完璧を目指すより、少しずつ楽しく取り組んでいける工夫が必要です。
6より上の段の計算が難しい
「5の段まではすんなり言えるのに、6の段から急に言えなくなる…」そんな声をよく聞きます。
数が大きくなるにつれて、答えの数字もどんどん大きくなっていくので、イメージがしにくくなってしまうんですね。
たとえば、2×2の次は2×3。
「4に2を足せば6」と、感覚でつかみやすいのですが、7×8の次の7×9となると、56に7を足して…と計算そのものが難しくなってしまいます。
さらに、6の段以降は「前に覚えた段でなんとなく答えられる」ことも、暗記が進みにくい理由の一つ。
たとえば、8×3を「3×8でしょ?」と置き換えてしまうと、本来覚えるべき8の段の感覚があやふやになってしまいます。
見かけは同じ答えでも、「8が3つある」と「3が8つある」は意味が違います。
本来は「8×3=24」と覚えなければならないのですが、代用してしまう子どもが多くいます。
ですが、そうすることで暗記できなくなってしまうのです。
特有の言い回しが頭に入りづらい
九九には、普段あまり聞き慣れない独特の言い回しがたくさん出てきます。
たとえば、「ごはしじゅう(5×8=40)」や「はっぱろくじゅうし(8×8=64)」など、同じ数字でも「ご・は・ぱ」と読み方が変わるので、子どもにとっては混乱のもとに。
3の段でも「さぶろく(3×6=18)」「さざんがく(3×3=9)」など、言い回しがバラバラで、初めて聞く子には「なんでこんな読み方なの?」と戸惑ってしまうこともあります。
リズムにのせて覚えやすくするための言い回しではあるのですが、慣れるまでは「言い方が難しいから、数字が頭に入ってこない…」と感じる子も少なくありません。
楽しく覚える実践テクニック
一見難しく感じる九九の暗記ですが、少しの工夫で楽しく覚えることができるんです。
ここでは、楽しく覚えるための実践テクニックを紹介します。
ぜひ参考にしてくださいね。
表を見ながら声に出して覚える
まずは「毎日目にすること」から始めましょう。
お風呂の壁やトイレのドア、子ども部屋の机の近くなどに九九表を貼っておくと、自然と目に入るので意識せずとも反復練習になります。
暗記カードやポスタータイプのグッズを活用するのもおすすめです。
声に出して読むことで、リズムや言い方も身につきやすくなります。
まずは2の段や5の段など、比較的覚えやすい段からスタートして、少しずつステップアップしましょう。
たとえばこんな流れで取り組むと◎
- 表を見ながら声に出して読む(リズム重視で)
- 見ないで暗唱してみる(慣れたらチャレンジ)
- 「3×4は?」「9×6は?」とクイズ形式で出題(ランダムにすると楽しい)
おうちの中でよく目にする場所に九九があるだけで、自然と頭にスッと入ってきます。
覚えるには“慣れること”が何よりの近道です。
歌やリズムで耳から覚える
声に出すだけでなく、歌やリズムを使った方法もおすすめです。
「ごーいちがご、ごーにじゅ~♪」とリズムに合わせて口ずさむだけで、不思議とするする頭に入ってきます。
最近では、YouTubeなどでさまざまな九九ソングが公開されているので、お子さんに合ったテンポや雰囲気のものを探してみるのも良いですね。
歌で覚える方法は、九九に苦手意識がある子でも「楽しい!」「もう1回!」と前向きに取り組めるのが大きなメリット。
ただし、ずっと歌に頼ってしまうと「7×8は?」と聞かれたときに、曲の頭から歌わないと答えが出ない…なんてことも。
また、逆から読んだり、バラバラに出題されたときは混乱しやすいので、学びの初期段階で「入り口」として使うのがおすすめです。
1の段から順番に覚える
九九表を見ながら声に出すことに慣れてきたら、次は“見ないで言ってみる”ステップへ。
いきなり全部を覚えようとせず、まずは1の段から5の段までの言いやすいところから始めるのがおすすめです。
「1の段、今日は全部言えた!」「5の段も覚えられた!」と、小さな達成感を重ねながら、徐々に進んでいきましょう。
6の段から9の段は、数が大きくなって難しく感じることもあるので、無理せずゆっくりでOK。
わからなくなったときは、すぐに九九表やカードで確認して大丈夫、見ないで言えるようになるまで何度も繰り返しましょう。
最初は難しいかもしれませんが、自然と身についていきますよ。
ランダム問題で練習する
1の段から順に言えるようになったら、今度はバラバラの順番で出してみましょう。
「7×3は?」「2×9は?」といったように、いろんな段から問題を出していきます。
順番どおりだとスラスラ言えても、ランダムになると「あれ…?」と迷うこともあるんです。
だからこそ、こうした練習を何度もすることで、しっかり頭に定着させていきます。
少しずつステップアップしていくと、どんな順番でも自信を持って答えられるようになるんです。
九九アプリを活用する
最近では、スマホやタブレットを使って、九九の練習ができるアプリもたくさん登場しています。
音声やイラストつきで読み上げをサポートしてくれたり、ランダムに出題してくれたりと、楽しく続けられる工夫がいっぱいです。
ゲームのような感覚で取り組めるので、「遊んでいるうちにいつの間にか覚えていた!」ということもあります。
ただし、スマホやタブレットを使う以上、他のアプリに気を取られてしまうこともあるかもしれません。
使う時間や場所を決めるなど、保護者の見守りがあると安心です。
家庭で保護者ができるサポート

学校の学習時間だけでは、九九を覚えきるのは難しいものです。
早く暗記できるようにするためには、できれば家庭でもサポートしてあげるのが理想的。
ここでは、保護者ができることを紹介します。
日常で九九に触れるようにする
九九をただ覚えさせるだけでなく、日常生活の中で「使う場面」をつくってあげると、子どもはぐんと理解しやすくなります。
たとえば、買い物のときに「このお菓子、1つ80円で3つ買ったらいくらかな?」といった声かけをしてみるのも一つの方法です。
九九が“勉強”ではなく“日常で役に立つ知識”だと感じられるようになると、自然と前向きに取り組めるようになります。
「役に立つから覚えるんだ」と実感できることが、九九への苦手意識を減らす大きなきっかけになりますよ。
表やカードなどのツールを用意する
九九の練習には、表やカードなどのツールを使うのもおすすめです。
特にフラッシュカードは、かけ算の式と答えだけでなく、読み方も一緒に書かれているものもあり、初めて覚える段階にぴったり。
声に出して読む練習にもつながるので、リズムよく覚えたいときにも効果的です。
市販のものだけでなく、インターネット上に無料でダウンロード・印刷できるカードもたくさんあります。
また、親子で一緒に手作りしてみるのもいいアイデア。
好きな色やイラストを入れながら作ることで、より楽しく、記憶にも残りやすくなります。
九九を定着させる秘訣
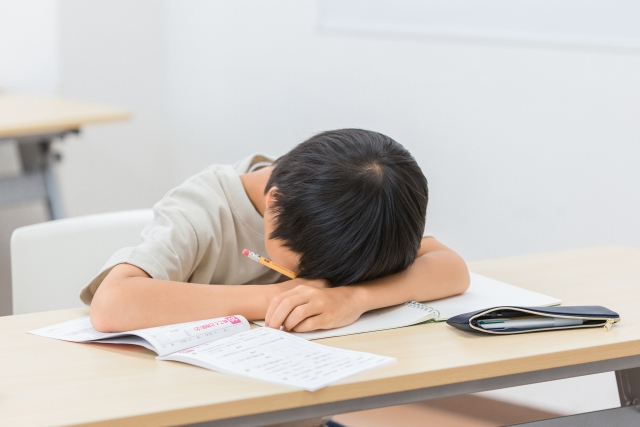
暗記できない子どもをみていて、「どうしてできないの?」と焦ってしまい、ただただ「暗記しなさい」と子どもに対して言ってしまっていませんか?
ですが、その方法は逆効果、九九に対する苦手意識が増していく一方です。
ここでは、九九を定着させる秘訣を紹介します。
急ぎすぎず、勉強を習慣にする
九九をなかなか覚えられなくても、焦る必要はありません。
覚えるスピードには個人差があり、「すぐにできなくても大丈夫」という気持ちで見守ることがとても大切です。
親が焦ってしまうと、その気持ちが子どもにも伝わり、「なんだかイヤだな…」と九九がますます嫌いになってしまうことも。
毎日少しずつ、短い時間でもいいので、無理なく続けることが習慣づけの第一歩です。
「今日はここまでできたね」と小さな達成を一緒に喜ぶだけでも、子どものやる気は大きく変わってきますよ。
完璧よりも「できた!」を褒める
九九の練習では、すべてを完璧に言えるようになることよりも、「少しでもできたこと」に目を向けて褒めてあげることが大切です。
暗記や算数が苦手な子どもにとって九九を覚えることは、長い道のりに感じてしまいます。
やっと1つの段を覚えられても、まだまだ覚えなければいけない段があったり、前回覚えた段を忘れてしまったりしていると、モチベーションが下がって諦めてしまうかもしれません。
新しい段を覚えられたときや、いつも間違えていた問題が言えたときなど、小さなことでも「よく頑張ったね!」「すごいね」と声をかけてあげましょう。
そうした言葉は、子どもの自信につながり、「もっとやってみよう!」と気持ちを高めてくれます。
できたことを一緒に喜ぶだけでも、勉強への前向きな気持ちがどんどん広がっていきますよ。
タイムを測ってゲーム感覚に
九九の暗唱やプリント練習をするときは、時間を測ってみるのもおすすめです。
「今日は何秒で全部言えるかな?」「昨日より早くなったかも!」と、ちょっとしたゲーム感覚で取り組めるようになります。
タイムを記録しておくと、覚える力がついてきたことが目に見えてわかるようになり、子ども自身も「できるようになってきた!」という実感が持てます。
こうした小さな成功体験は、九九へのやる気を高めるだけでなく、算数そのものに自信をもてるきっかけにもつながっていきます。
どんどん早く言えるようになることを一緒に喜びながら、楽しく続けていきましょう。
まとめ
小学2年生以降の学びに欠かせない大切なステップである「九九」。
ですが、ただ詰め込んで覚えるだけでは、すぐに忘れてしまったり、「苦手かも…」という気持ちが残ってしまうことも。
大切なのは、子どもが自分のペースで、少しずつ“わかる・できる”を積み重ねていくことです。
表やカード、歌、アプリなど、子どもに合った方法を取り入れながら、遊びのように楽しく続けていける工夫をしていきましょう。
「覚えること」だけにとらわれず、日常の中で九九を使ってみたり、「できた!」をたくさん褒めてあげたりすることが、やる気と自信につながります。
家庭でのあたたかいサポートがあれば、九九はきっと、子どもにとっての“得意”に変わっていきますよ。
関連するコラム
習い事を検索
-
- (428件)
-
-
-
-
-
-









