学童保育の基礎知識:放課後安心して子供を預けるために

小学校入学後、共働き家庭を中心に入会を検討する学童保育。「そもそも学童保育はどのような場所なの?」「放課後子ども教室とは何が違うの?」など、気にしている保護者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、学童保育の概要と種類、学童保育選びのポイントなどを紹介していきます。ぜひ最後までお読みいただき、学童保育について理解を深め、子どもに合った学童選びの参考になれば幸いです。
学童保育とは?
学童保育は保護者が就労しているなどの理由で、放課後や学校休業日に自宅で過ごすことが難しい児童へ遊びと生活の場を提供する施設です。
学童保育の定義
学童保育は学童クラブ、放課後児童クラブ、児童クラブなど、地域や施設によってさまざまな名称で呼ばれていますが、どれも児童福祉法における「放課後児童健全育成事業」のことを指します。
こども家庭庁によると、放課後児童健全育成事業は以下のように定義されています。
『児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものです。』
— 引用:こども家庭庁 https://www.cfa.go.jp/policies/kosodateshien/houkago-jidou/
放課後や土曜日、長期休暇中に開所し、子どもたちが安心して過ごせるように放課後児童支援員が環境を整え、見守りをする施設です。対象学年は小学1年生から6年生が多いですが、地域や施設によっては定員の関係で小学3年生頃までを対象にしているところもあります。
児童の見守りをする放課後児童支援員は、保育士資格や教員免許などを持つか、高卒以上で2年以上の児童福祉施設での実務経験を持ち、自治体が実施する放課後児童支援員認定資格研修を修了した職員です。おおむね児童40名以上に対して2人の支援員の配置が必要ですが、うち1人を除いて補助員(無資格者)への代替が可能とされています。
学童保育の現状(待機児童と保育の質の問題)
保育園の待機児童は減少していますが、学童保育はニーズが増え続けていることで待機児童が多い状況です。こども家庭庁の「令和6年 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況」によると、令和6年の待機児童数は全体で17,686人で、前年度よりも1,410人増加しており、増加傾向が見られます。学年別内訳を見ると、小学3年生は3,879人、4年生は5,707人で、中学年以降の待機児童も目立ち「小4の壁」と呼ばれることがあります。学童保育の入会は低学年の児童が優先されることが多いため、中学年以降は退会扱いとなってしまい、待機児童として登録されるケースも多いです。また、優先順位が高い小学1年生でも2,209人の待機児童がおり、各自治体で受け皿の確保を急いでいます。
増え続けるニーズに応えて待機児童を少しでも減らすために、定員を超えて子ども達を受け入れている学童保育も少なくありません。定員を超えて受け入れることで、部屋の広さに対して子ども達が多い状態になるため、トラブルも多くなります。
また、支援員は学校がある日は放課後の時間を中心に仕事をし、学校がない日はシフト制で午前中から夕方まで勤務します。勤務時間が流動的ということもあって人員確保が難しく、資格を持たない補助員も多くいるため専門性が不十分ではないかと問題視されているのが現状です。
学童の種類:特徴と料金について
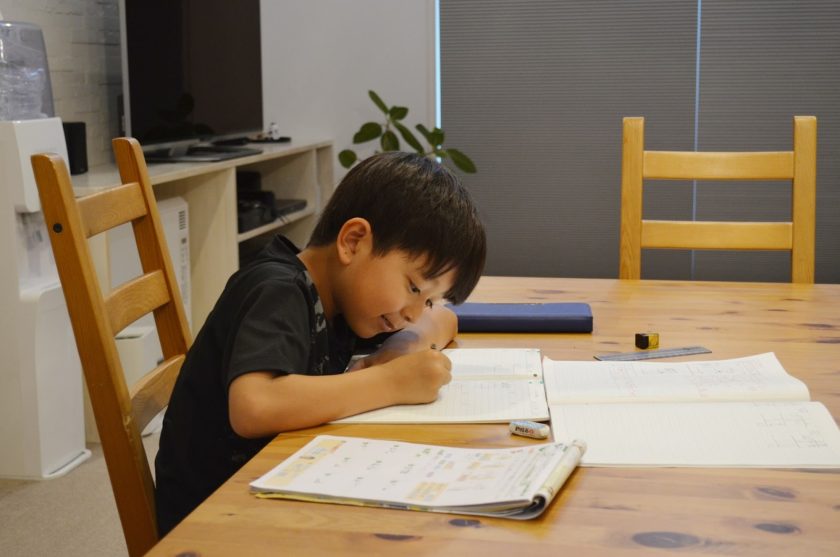
学童保育の主な形態には、放課後子ども教室、公設学童クラブ、民間学童クラブの3つがあります。それぞれの特徴について紹介します。
まずは比較表をご覧ください。
| 放課後子ども教室 | 公設学童保育 | 民間学童保育 | |
| 運営主体 | 自治体・PTA・地域団体など | 自治体(運営は民間に委託している場合あり) | 民間企業・社会福祉法人・NPOなど |
| 利用対象 | 小学校に通うすべての児童 | 共働きや療養が必要な家庭の小学生 | 施設により異なるが、利用条件がない場合もある |
| 利用条件 | 誰でも参加可能 | 保育の必要性を証明できる書類提出が必要 | 施設が定める所定の契約・申し込みが必要 |
| 利用時間 | 放課後の数時間週に数回程度の実施、学校休業日にしている場合もあるなど地域により様々 | 下校後~18時頃学校休業日は8時~18時頃 | 基本的に下校後~19時頃(夕食提供して21時頃まで対応している施設あり)学校休業日も対応 |
| 活動内容 | 遊び・学習支援・工作など | 宿題・おやつ・遊び | 宿題・おやつ・遊びを中心に、プログラミング・英語・習い事など独自プログラムがある施設も |
| 料金 | 原則無料(材料費・おやつ代などが必要になることも) | 月額数千円〜1万円前後 | 月額2万〜5万円以上(施設によって差あり) |
| 実施場所 | 小学校の空き教室など | 小学校の空き教室や児童館など | 施設・商業ビル内・習い事教室など |
| 職員 | 地域のボランティアが中心 | 放課後児童支援員・補助員 | 有資格者でない場合もあり(施設により異なる) |
放課後子ども教室
放課後子ども教室は、学校の空き教室などを利用して異学年や地域住民と交流したり、遊びや学習の機会を提供したりしています。学童保育は利用のための手続きや審査が必要ですが、放課後子ども教室は保護者の状況に関係なく利用できることが特徴です。
小学校の敷地内で実施されるため保護者の送迎が不要なことも多く、原則無料で利用できるため金銭的な負担が少ないことがメリットとして挙げられます。あくまでも活動の場を提供する事業のため、長時間の預かりを前提としていないことが多いですが、地域によっては学童保育と一体となって事業を行っているケースがあります。
公設学童保育
公設学童保育は自治体が設置しており、運営も自治体が行う場合と民間に委託している場合があります。小学校内の空き教室や学童クラブ室、児童館などで実施されることが多く、国や自治体の補助金で運営されているため、利用料が月額4,000円〜1万円程度と比較的安いことが特徴です。
保育園の入所審査と同様、保護者が就労・療養していることが利用条件となることが多く、待機児童が多い施設では入所審査で低学年の児童、母子家庭の児童などの優先順位が設けられています。
民間学童保育
民間学童保育は、民間企業や社会福祉法人、NPOなどが運営する学童保育です。商業施設や習い事教室など利便性の高い場所で開設していることも多く、公設学童保育に比べてサービス内容が充実している施設が多いのが特徴です。一例を紹介します。
- 夕食提供があり、21時頃まで預かり可能
- 保育時間内で英語やプログラミングなどの専門的なカリキュラムを提供
- 敷地内に習い事教室があり、送迎不要で習い事が可能
- 学校から学童まで、学童から自宅までなど、送迎バスが利用できる
サービスが充実している分、料金は公設学童保育に比べて高額で月額2万円〜8万円程度が相場です。入所条件は施設によって異なり、保護者の就労や療養を条件にしていない施設もあります。働く保護者だけでなく、教育に力を入れたい保護者からも人気を集めています。
学童保育を選ぶ際のポイント
子どもが放課後を安心して楽しく過ごすためには、家庭の状況や子どもの性格に合った学童保育を選ぶことが大切です。できれば申し込み前に見学し、次のようなポイントを確認してみましょう。
通いやすさ
学童保育を選ぶポイントのひとつが、通いやすさです。小学校や家からの所要時間や経路を確認しましょう。小学校から学童保育への移動は子どもが行うため、毎日負担にならずに通える範囲で選ぶことがおすすめです。
特に低学年のうちは、お迎えや学校休業日は保護者が送迎をすることが多くなります。保護者の仕事の状況や通勤経路から見て、送り迎えがしやすいと負担が少なくなり、おすすめです。送迎が難しい場合は、送迎バスの有無や、急な残業が発生したときの延長保育の対応についても事前に確認しておきましょう。
施設を利用可能な時間
学童保育の利用時間は、施設や時期によって異なります。平日や長期休暇中、土曜日など、保護者の働き方に合わせて、利用できる時間帯をしっかり確認しておきましょう。
公設学童は、平日の下校時から18〜19時頃まで利用可能なことが多いですが、施設によっては17時頃に子どもだけで帰宅させるケースもあるため、事前に確認しておくことがおすすめです。土曜日や長期休暇などの学校が休みの日は、8時頃から開所していることがほとんどです。
民間学童はさらに遅い時間まで対応している施設もありますが、延長料金が別途かかることが多いため、料金や夕食提供の有無・内容を確認しておきましょう。
また、気象警報発令時やインフルエンザなど感染症での学校閉鎖・学級閉鎖時には、学童を閉所したり、学級閉鎖しているクラスの子どもは預かりができなかったりする施設もあります。見学時に支援員に確認する、学童に通っている子どもがいる先輩ママ・パパに聞いてみるなど、入会前に確認しましょう。
利用料金
学童保育の利用料金は、運営主体によって大きく異なります。
- 公設学童保育:比較的安価な料金設定だが、おやつ代やイベント費用などが別途徴収される場合もある
- 民間学童保育:サービス内容に応じて料金が設定され、送迎サービスや特別なカリキュラムが含まれていると高額になりやすい
各施設の料金体系を事前に確認し、予算に無理のない範囲で選ぶことが大切です。
学童の雰囲気
子どもが毎日通う場所だからこそ、施設の雰囲気を重視することが大切です。見学時には、子どもたちがどのような表情で過ごしているか、支援員と子どもたちの関係性などを観察しましょう。
子どもたちが自由に遊んでいるか、決められたプログラムに沿って活動しているかなど、学童ごとの方針も施設によって異なります。子どもに合う雰囲気の施設を選ぶことで、学童生活がより充実したものになります。
学童保育に関するよくある質問

保護者の方が抱きやすい学童保育の疑問をまとめました。
学童保育ではどんなことをしますか?
公設学童では子ども達が自主的に遊んだり、宿題に取り組んだりする時間が中心ですが、夏休みやクリスマスなどにイベントを実施することもあります。室内では読書やぬりえ、折り紙、工作、おもちゃなど、屋外では学校の校庭や近隣の公園に行くことが多いですが、子ども達が自分で遊びを選んで自由に遊ぶことが大半です。
民間学童では、英会話やプログラミング、スポーツなどの専門的な習い事がカリキュラムに組み込まれている施設もあります。
夏休みなど長期の休みの期間も利用可能ですか?
公設・民間学童保育であれば、夏休みや冬休みなどの長期休暇中も利用できます。ほとんどの施設は平日の午前中から開所しており、1日を通して子どもたちを預かる体制を整えています。
特に公設学童保育では夏休み期間中に利用者が増加するため、事前に申し込みや登録が必要となる場合があります。また、長期休暇中の利用は、通常時と料金体系が異なる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
子どものアレルギーには配慮してもらえますか?
事前に施設側に相談することで、配慮してもらえる場合がほとんどです。おやつを提供する施設ではアレルギーに対応したおやつを用意したり、持参を許可したりするなどの対応が取られています。
食物アレルギー以外にも、花粉やほこりなどのアレルギーがある場合も、事前に施設に伝えておきましょう。緊急時に適切な対応が取れるよう、かかりつけ医やアレルギーの詳細について、書面などで共有しておくと安心です。
まとめ
学童保育は、子どもが放課後を安全に過ごせる環境を整え、保護者の仕事と子育ての両立を支える大切な存在です。公設学童保育・民間学童保育・放課後子ども教室といった多様な選択肢がある一方で、それぞれの特徴や利用条件、料金体系は大きく異なります。待機児童や人員配置の課題など、現状の課題も理解したうえで、子どもに合った学童保育を選ぶことが大切です。通いやすさや支援体制、施設の雰囲気などを見極めるために見学や情報収集を行い、ご家庭にとって無理のない選択を心がけましょう。
関連するコラム
習い事を検索
-
- (428件)
-
-
-
-
-
-









