読書の力で子どもの未来を育む!読書習慣から得られるメリット

「うちの子、本を全然読んでくれなくて…」そんなふうに感じたことはありませんか?
なかなか読もうとしない姿を見て、「無理に読ませる必要ってあるのかな?」と疑問に思うこともありますよね。
しかし、読書には子どもの心や力を育てる、たくさんのメリットがあります。
「本を読むようになって人生が変わった」「読書が自信につながった」という声も聞かれるほどです。
この記事では、読書が子どもの未来にどんな良い影響をもたらすのかをご紹介します。
読書がもたらすメリット
読書には心が育ったり、言葉の力がついたり、人との関わり方にも良い影響があります。
ここでは、読書が子どもにもたらしてくれるさまざまなメリットを紹介します。
ボキャブラリーが増える
本を読むと、「こんな言い方があるんだ!」「この言葉、初めて聞いた!」という発見がたくさんあります。
普段の会話や授業ではあまり出てこないような言葉にも出会えるのが、読書のおもしろいところです。
例えば、「嬉しい」という表現一つをとっても、「ワクワクする」「心が踊る」など、いろいろな種類がありますよね。
本では、そうした言葉を自然と学ぶことができます。
そして何度も触れていくうちに、少しずつボキャブラリーが増えていきます。
語彙が豊かになると、気持ちや考えを自分の言葉で伝える力が育ちます。
さらに、表現力がアップすることで作文やテストの文章問題でも力を発揮できるように。
読書は、言葉を覚えるだけでなく、伝える力・考える力も育ててくれるのです。
読解力の向上
子どもは、本を読むとき「この人はなぜこんなことを言ったんだろう?」「この先どうなるのかな?」と、内容を考えながら読み進めています。
この“考えながら読む”ことが、読解力を育てるポイントです。
読解力とは、文章の意味をきちんと理解したり、行間から気持ちを読み取ったりする力のこと。
話の流れを掴むのが上手くなったと感じるようになったら、読解力が伸びている証かもしれません。
教科書の文章を勉強として読むよりも、物語の世界に入り込んで楽しみながら読む方が、自然と読解力は身についていきます。
読書には、語彙力と一緒に読解力も伸ばしてくれる、そんな一面もあるのです。
論理的思考が身につく
物語には「起承転結」や「原因と結果」など、一定の流れがあります。
読書を通じて子どもがその構成に慣れていくことで、物ごとを順序立てて考える力が少しずつ育っていきます。
こうした力は“論理的思考”と呼ばれ、問題を整理したり、自分の考えをわかりやすく伝えたりするときに役立ちます。
例えば、論理的思考力が身につけば「どうしてそう思ったのか」「何が問題だったのか」といった問いにも、自分なりに筋道を立てて答えられるようになります。
論理的思考は、学習面だけでなく将来的な仕事や人間関係にも影響する大切な力です。
読書はその基礎を、日々の中で無理なく育ててくれます。
想像力の向上
子どもは、物語を読み進める中で、登場人物の気持ちや行動の理由を考えたり、次に何が起こるのかを想像したりしています。
特に小説のようなストーリー性のある本では、文字だけの情報をもとに、自分の中で物語の場面をイメージする力が働きます。
こうした体験の積み重ねが、目に見えないことを思い描く力、想像力を育てていくのです。
想像力は、創造的な発想に役立つだけでなく、人の気持ちや立場を思いやる力にもつながります。
相手の気持ちをくみ取る力が育つことで、コミュニケーションや人間関係もより豊かなものになっていくでしょう。
集中力の向上
子どもは本を読むとき、集中して内容を理解しようとします。
特に、自分の好きなジャンルやシリーズに出会ったときには、何時間も静かに読み続けることもあるでしょう。
こうした経験を重ねていくことで、「一つのことにじっくり向き合う力」が自然と身についていきます。
また、長時間読書することで、集中力の深さだけでなく、持続性の向上も期待できます。
知識を得られる
読書では、知らないことに出会える貴重なきっかけを得られます。
例えば、恐竜の本を読んで生き物に興味を持ったり、偉人の伝記をきっかけに歴史が好きになったりと、本を通して知識の世界がどんどん広がっていきます。
学習につながるだけでなく、子ども自身の「知りたい」「もっと学びたい」という気持ちを育ててくれるのも、読書の大きな魅力です。
経済や歴史、文学、哲学、社会、政治、経営など、さまざまなジャンルの本に触れることで、自然と知識の幅も広がります。
興味のあるテーマを集中的に読むのもいいですし、いろんな分野の本に触れて、自分の中にたくさんの“引き出し”をつくっていくのもおすすめです。
リフレッシュ効果によるストレスの解消
読書には気持ちを落ち着け、心をリセットするリフレッシュ効果があります。
英国サセックス大学の研究では、たった6分の読書でストレスが最大68%軽減されたという結果が出ており、その効果は音楽や散歩よりも高いとされています。
どんな時間帯に読んでもストレスの解消はできますが、その効果を最大化するためには就寝前がおすすめです。
ただし、ワクワクして続きが気になる本や夢中になって止まらなくなる本だとかえって頭が冴えてしまうので、選ぶ本には注意が必要です。
大阪府立大学名誉教授の清水教永先生は、「眠りにつきやすくするには、続きが気になる本よりも、少し退屈なくらいの本が最適」と語っています。
寝る前のほんの10分でもかまいません。
気軽に読める1冊を読むことで、子どもはリラックスした状態で眠りにつくことができ、より良い睡眠をとることができるでしょう。
楽しみながら読書習慣を育むポイント
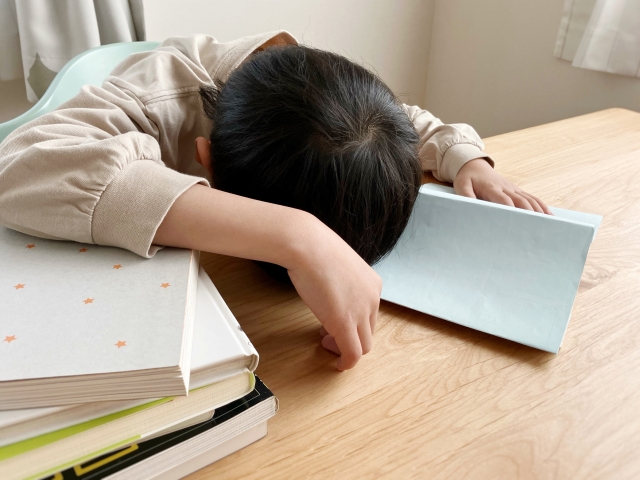
読書を習慣化させたいと思って、無理やり本を与えても、子どもは本を読もうとはしません。
読書を習慣化させるためには、楽しんでもらうことが1番です。
ここでは読書週間を育むためのポイントを紹介します。
読み聞かせで本を好きになってもらう
聞くことに集中できる読み聞かせでは、子どもは物語そのものの楽しさをじっくり味わうことができます。
自分で読むと、どうしても「読めない漢字」や「難しい言葉」に意識が向きがちですが、読み聞かせではストーリーがすっと入り込んできます。
登場人物の気持ちに共感したり、先の展開をわくわく想像したりするうちに、「本っておもしろい」と感じる心が育ちます。
読書へのハードルを下げて、本を身近な存在にして好きになってもらう。
その第一歩が、読み聞かせなのかもしれません。
家に子供が楽しめる本を用意する
子どもが読んでみたいと思える本を家に用意しておくことも、とても大切です。
好きな本をすぐ手に取れる環境があると、それだけで子どもは「本読もうかな」という気持ちになってくれます。
例えば、0〜2歳なら音やリズムを楽しめる絵本、3〜4歳はストーリーのある絵本、5〜6歳なら少し長めのお話や図鑑など、年齢に合った本を選んであげるのがおすすめです。
また、恐竜や電車など、そのときハマっているテーマを選ぶのも効果的です。
本棚は子どもの目線に合わせて、いつでも自由に手に取れるようにしておくのがポイント。
「おもしろそうな本がある」「読んでみたいと思ったときにすぐ読める」、そんな環境づくりが、本を好きになるきっかけになります。
親も同じ本を読む
保護者の方は、最近本を読んでいますか?
もし読書の習慣がないまま「本を読みなさい」と声をかけても、子どもにはなかなか響きません。
子どもは親の言動を真似したがるもの。
そのため、まずは保護者が本を楽しむ姿を見せることで、子どもも自然と読むようになります。
子どもが読んでいる間に保護者は別の本を読むのでも問題ありませんが、おすすめなのは同じ本を読むことです。
内容を共有できると、本を読む時間がもっと特別な時間になります。
例えば、学校から借りてきた本を一緒に読んでみて、「ここが面白かったね」「あそこはどう思った?」と感想を話すだけでも、本に対する関心が自然と育っていくものです。
スマホ・タブレットの活用
スマホやタブレットの普及によって、子どもが本から離れてしまうのでは…と心配になることもあるかもしれません。
けれど、あえてそのデジタル環境を読書に活かしてみるという方法もあります。
最近は、絵本や児童書、小説が読めるアプリも充実しており、ちょっとしたスキマ時間にも手軽に読書が楽しめます。
画面の見すぎによる目の疲れには注意しながら、現代ならではの“新しい読書の形”として取り入れてみるのもひとつの方法です。
読書のデメリット
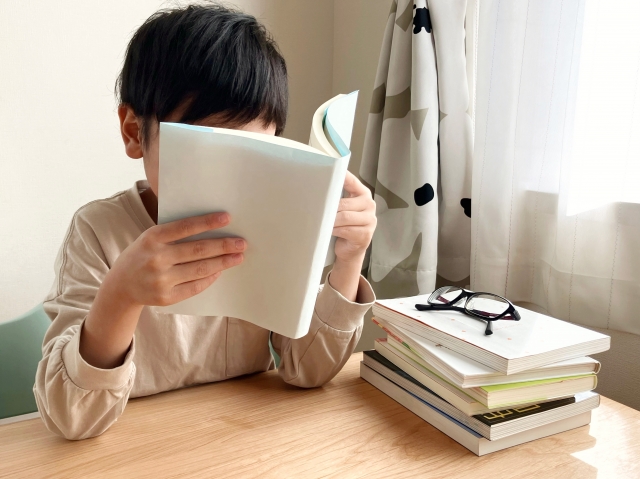
さまざまなメリットがある読書ですが、残念ながらいくつかのデメリットもあります。
ここでは、読書をすることでのデメリットと対策を紹介します。
目を酷使する
読書はどうしても目を使うものです。
特に集中して長時間読み続けていると、目の疲れが溜まりやすく、視力に影響することもあります。
本は基本的に近い距離にピントを合わせて読むため、遠くを見ない時間が長くなると、目の調整力が低下しやすくなります。
「読書のあとに遠くがぼやける」といったことがあれば、注意が必要です。
目の負担を軽くするためには、読む時間やページ数をあらかじめ決めておくのがおすすめです。
また、目のピント調整をするためには、途中で窓の外を見たり、遠くの景色を意識したりすることも効果的です。
読書を楽しむためにも、定期的な休憩を意識して取り入れていきましょう。
運動不足になる
読書は静かに過ごす時間として有意義ですが、長時間座ったままになることで運動不足になります。
特に成長期の子どもにとっては、体を動かすことも心や身体の発達に欠かせません。
例えば、夢中になって1〜2時間本を読んでいたら、その分外遊びや運動の時間が減ってしまいますよね。
読書の合間に軽いストレッチをしたり、時間を区切って外遊びの時間をあらかじめ予定に入れたりしましょう。
お金と時間がかかる
当然のことながら、読書にはお金と時間がかかります。
絵本や児童書は1冊1,000円前後するものが多く、シリーズものを揃えようとすると、思った以上に費用がかさむこともあります。
図鑑や大型絵本などはさらに高額になるでしょう。
また、1冊の本を読み終えるにはある程度の時間が必要です。
内容にもよりますが、数十分で読めるものから、何時間もかかるものまでさまざまです。
図書館の利用や古本の活用、フリマアプリなどを上手に取り入れれば、費用を抑えて本を楽しむことができます。
また、スキマ時間を活かして少しずつ読み進めるなどすれば、無理なく続けられるようになりますよ。
まとめ
読書には、語彙力や読解力、想像力、集中力など、子どもの成長に役立つメリットがたくさんあります。
さらに、気持ちを落ち着けたり、ストレスをやわらげたりと、心にもいい影響を与えてくれるのが読書の魅力です。
もちろん、時間やお金がかかる、運動不足になりやすいといった面もありますが、工夫しながら取り入れていけば、楽しく続けることができます。
「読書って楽しい」「本っておもしろい」と感じられるような環境づくりや関わり方が、本を好きになってもらう第一歩になります。
子どもにとって、本が身近な存在になるよう、できることから少しずつ始めてみてはいかがでしょうか。
関連するコラム
習い事を検索
-
- (428件)
-
-
-
-
-
-









