子どもの成長を支える!年齢別しつけのポイントと親ができること
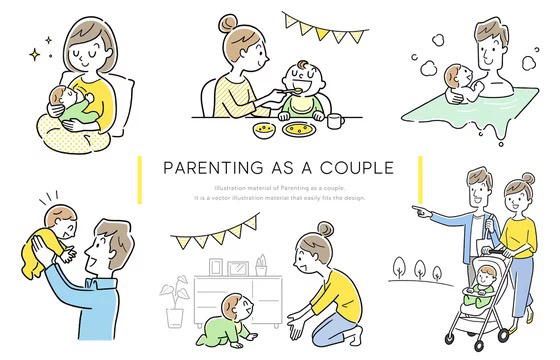
子どものしつけは、成長に合わせて変えていくことが大切です。
しかし、「しつけはいつから始めるべき?」「どんな叱り方が効果的?」と悩むことも多いのではないでしょうか。
間違った方法は逆効果になることもあるため、NGなしつけ方法も知っておきたいところです。
この記事では、年齢別に適したしつけのポイントと、親ができることを詳しく解説します。
子どもの成長をしっかりと支えられるよう、ぜひ参考にしてくださいね。
なぜしつけが必要?子どもの成長における役割
しつけと聞くと、つい厳しい訓練や強制をイメージする方もいるのではないでしょうか。
しかし、しつけとは本来、「~しなければならない」と押しつけるものではなく、子どもが将来、自分らしく幸せに生きるための行動習慣を育てることです。
子どもの成長におけるしつけの役割について、詳しく確認していきましょう。
社会性を身につける基礎
しつけの大きな役割の1つが、社会性を育むことです。
人は生きていくために、生活習慣や社会のルールを身につけなければなりません。
たとえば、食事や身支度を自分で行うこと、時間を守ること、他者と適切な関係を築くことなどが挙げられます。
こうした力は、一朝一夕で身につくものではなく、幼少期からの積み重ねが重要です。
しつけとは、親が子どもに社会で生きていくための基盤を教えることでもあります。
日々の関わりを通じて、子どもは少しずつ社会の中での振る舞いを学び、自立へと向かっていくのです。
自己肯定感を育むために
しつけで最も大切なのは、子どもが「自分は大切な存在だ」と感じられる環境をつくることです。
「努力することの大切さ」を学んでほしいと願うあまり、過剰なしつけをしてしまう親もいます。
例えば、年齢に見合わない高いレベルの勉強やスポーツを強要したり、指示に従わなかったときに極端に厳しい態度をとったりすることは、しつけではなく子どもの心を傷つける行為になりかねません。
子どもにとって親とは最も近い存在であり、唯一の味方と言える存在です。
子どものためのしつけだと思っていても、そんな存在である親から厳しい言葉ばかりを浴びせられると、「自分は価値のない人間なのかもしれない」と感じてしまうこともあります。
しつけの本質は、子どもを親の理想通りに育てることではありません。
厳しさの中にも愛情や思いやりを忘れず、子どもの気持ちに寄り添った関わりを心がけましょう。
年齢別しつけの具体例と親の関わり方
しつけは、子どもの成長に合わせて関わり方を変えていくことが重要です。
幼児期と学童期では、身につけるべき生活習慣や社会性が異なり、親の関わり方も変わってきます。
例えば、幼児期には基本的な生活習慣やルールを教えることが中心ですが、学童期になると自立を促しながら見守る姿勢が求められます。年齢ごとにどのようなしつけが必要なのか、具体的な例とともに親の関わり方を紹介します。
【乳児期】信頼関係を構築し”危険なこと”を教える
乳幼児期のしつけで大切なのは、親子の信頼関係を築きながら、危険なことを教えることです。
0歳のうちは言葉を理解することがほとんどできません。
叱るよりもスキンシップや優しい声かけで「愛されている」と感じさせることが重要です。信頼関係がしっかり築けていれば、成長してから叱る場面でも恐怖ではなく、のびのびと成長できるようになります。
生後10ヶ月頃からは危険を教えることが最優先です。
ライターや刃物に触れようとしたときは、「ダメだよ」「危ないよ」と真剣に伝え、行動を止めましょう。
1〜2歳になると、好奇心が旺盛になり、「してはいけないこと」を伝える段階に入りますが、この時期は繰り返し優しく教えることが大切です。
イヤイヤ期には、少しずつ言葉を理解できるようになっていますが、それでも従うことはできません。
それは、「理性」を司る脳の部位である前頭前野が発達途中だからだと言われています。
無理に叱るのではなく、共感して気持ちを受け止めたり、提案してみたりするのが効果的です。
【幼児期】生活習慣の自立と社会性を育む
幼児期(1~5歳)のしつけでは、生活習慣の自立と社会性を育むことが大切です。
例えば、「スプーンを自分で持つ」「トイレに行くタイミングを伝える」など、自立を少しずつ促します。
また、友達との関わりで協調性を養い、小学校に向けて社会性を身に着けることも大切です。
おもちゃを「貸して」「どうぞ」とやり取りしたり、公園で「順番を待つ」ことを教えたりするなど、ルールを守る経験を増やしていきましょう。
しつけのポイントは、一貫性を持って伝え、できたときにしっかり褒めることです。
例えば、自分で靴を履けたときに「自分で履けたね、すごいね」と褒めることで、子どもは次も頑張ろうと思えます。
決まりは1度に押しつけず、少しずつ学ばせること。
簡単なルールから始め、できたことを褒めながら他のルールも教えていきましょう。
【学童期】自立心を養い、学習習慣を身につける
学童期は自立心や学習習慣を育む大切な時期です。
親は過度に干渉せず、適度なサポートを心がけましょう。
例えば、「今日はどの服を着るか自分で決めてみよう」といった小さな決定を任せることで、責任感が育ちます。
失敗したときは叱らず、「次はどうすればいいかな?」と一緒に考えることで、自信を失わず次に進めます。
学習習慣は、無理に勉強を押しつけず、15分程度の短時間で取り組むことから始めましょう。
例えば、15分集中したらシールを貼るなどのご褒美を設けると、前向きに取り組みやすくなります。勉強しない日でも、机の前に2〜3分座るだけでもOKです。
焦らず、無理なくサポートしていきましょう。
子どものタイプ別!困ったときのしつけ方
子どもの性格や行動を理解し、適切なしつけをすることがポイントです。
ここでは、タイプ別に効果的なしつけ方法を紹介します。

自己主張が強い子どもへの対応
子どもが何かを主張したときは、まずしっかりと話を聞いて、その気持ちを理解してあげましょう。「テレビを見たいんだね」と言ってあげるだけで、子どもは自分の気持ちをちゃんと受け止めてもらえたと感じます。
許せることと許せないことはしっかり伝え、例えば「人に迷惑をかける」「危険なこと」「ルールを破ること」はダメだよ、と教えることが大切です。
社会性を身につけるために、わかりやすく説明してあげましょう。
また、失敗から学ぶこともあるので、少しの失敗は経験としてやらせてみましょう。
もし納得しない場合は、「別の話題に切り替える」と気を逸らして落ち着かせることができます。
「今日のご飯は何食べたい?」など、子どもの興味を引く話題で気分転換を図ってみてください。
内気で引っ込み思案な子どもへの対応
引っ込み思案な子どもは、小さな成功体験を積み重ねることで自信に繋がる傾向がありまます。
例えば、「今日も自分から挨拶ができたね、素晴らしいよ」と褒めることで、自己肯定感が育まれます。
また、子どもの長所に注目して、「君はとても慎重で考える力があるね」と伝え、積極的になれる環境を作りましょう。
失敗を恐れさせず、「次はこうしてみようね」と前向きなアドバイスをすることが大切です。
兄弟げんかが絶えないときの対応
けがに進展する恐れのない場合には、親は干渉しない方がいいでしょう。
最も避けるべきことは、喧嘩の流れを理解せずに上の子を頭ごなしに叱ることです。
それでも喧嘩がエスカレートしていった場合は、まず平等に2人の話を聞き、感情が高ぶっている子どもたちの思いを代弁して伝えましょう。
兄弟が仲良くしている時は、お互いの良い点を褒め、比較を避けることが重要です。
また、喧嘩自体のルールを決めておくのもおすすめです。
そのルールは、親が勝手に決めるのではなく、兄弟交えてみんなで相談して決めると、守ろうという気持ちが強くなります。
やってはいけない!間違ったしつけと改善策

体罰・暴言はNG!子どもの心への影響
子どもの人格を否定するような叱り方は絶対に避けましょう。
「あなたはダメな子ね」や「本当に悪い子ね」といった言葉は、子どもの自己肯定感を低くし、自信をなくさせ、ネガティブな思考を引き起こします。
人格を否定することなく、行動に焦点を当てて指摘することが大切です。
また、叩くなど恐怖感を与えることもNGです。
暴力はしつけではなく、子どもに不安を与えるだけで、暴力に対する耐性を作り、将来的に他人に対して暴力をふるう可能性も高まります。
冷静に言葉で伝えるよう心がけましょう。
過干渉・放置もNG!子どもの成長を阻害する
「過保護」と「放任」は一見、真逆の育児方法に思えますが、実はどちらにも共通の問題があります。
それは、子どもに自分で解決する方法を教えていないことです。
心理学では、魚を与えるのではなく、釣り方を教えることで自立する力が育つという例があります。
過保護だと親が手を出しすぎ、放任だと子どもが方法を学ぶ機会を逃してしまいます。
大切なのは、どちらでもなく、子どもに「やり方」を教えて、自立をサポートすることです。
親自身のストレスケアも忘れずに
子育てにはイライラする瞬間もありますよね。
子どもが言うことを聞かない時や思い通りにいかない時、感情的になることもあるかもしれません。
そんな時には、まず深呼吸をして気持ちを落ち着けましょう。
3回深呼吸をして6秒数えるだけでも、心がスーッと落ち着きます。
また、感情が高ぶった時はその場を離れて冷静さを取り戻すのも効果的です。
誰かに悩みを打ち明けるのも良い方法の1つです。
電話やLINEで話してみたり、相談窓口に頼ることで気持ちが楽になります。
自分だけで抱え込まず、適切なサポートを受け、心身共に披露してしまう前に、ご自身のストレスケアにも気を配ってくださいね。
子どものしつけに関するよくある質問
子どものしつけについては、悩みや疑問が尽きません。
日々の育児の中で、親としてどのように対応するべきか迷う場面も多いものです。
ここでは、子どものしつけに関するよくある質問にお答えします。
しつけと虐待の違いは?
しつけは子どもが社会で適切に振る舞えるように教えることですが、虐待は子どもの心身を傷つける行為です。
しつけは愛情と適切な指導をもって行うもので、子どもの成長を助けますが、叩くや殴るといった暴力や過剰な言葉、無視といった子どもを傷つける行為は虐待に該当します。
パパ・ママでしつけ方針が違うときは?
パパとママのしつけ方針が違うことは珍しいことではありません。
まずお互いの意見をしっかりと話し合い、共通の方針を決めることが大切です。
それでも折り合いのつかないときには、子どもの興味から判断したり、第三者の意見を取り入れるのもおすすめです。
叱っていいのはどんな時?
子どもを叱る場面は、安全に関わる時や、社会的なルールを守っていない時です。
例えば、道路に飛び出そうとしたり、危険な場所に近づこうとした場合は、しっかり叱ることが大切です。
また、公共の場で騒いだり、友達を傷つけるような行動を取ったときにも、叱ることでルールやマナーを教えましょう。
こうした叱り方は、子どもが安全に過ごし、社会で生きていくうえでの大切な学びとなります。
まとめ
子どものしつけとは、単なる厳しい訓練ではなく、善悪やルールを教え、子どもが自分の行動や言動をコントロールできるようにすることです。
年齢ごとによるしつけの方法を知っておくことで、子どもが将来困らない基盤を作ることになります。
叱るべき時は、安全や社会的ルールに関わる場合で、感情的にならず冷静に伝えることが重要です。
親は過保護や放任にならず、子どもが自分で考え、行動できる力を育むサポートを心がけましょう。
子どもの成長を支えるために、しつけの方法を見直し、日々の育児を楽しんでくださいね。
関連するコラム
習い事を検索
-
- (428件)
-
-
-
-
-
-









