子どもの学習効率をアップ!やる気を引き出す勉強のやり方ガイド

勉強には悩みがつきもの。
「勉強しなさい」と声をかけても、なかなか机に向かわなかったり、すぐに気が散ってしまったり…そんな子どもの姿に悩んでいる保護者の方も多いのではないでしょうか。
たとえ同じ時間を勉強に使っていたとしても、やり方によって成果の出方は大きく変わります。
せっかくなら、効率よく勉強できて、子どものやる気が自然と引き出せる方法を知りたくありませんか?
この記事では、勉強がうまく進まない理由を整理しつつ、子どもが前向きに取り組める勉強法や気をつけたいポイントを解説していきます。
勉強が捗らない理由
勉強しようと思っても、なかなか気が向かない…。
そんな経験は、子どもだけでなく保護者の皆さんもしたことがあるのではないでしょうか。
効率を高めるには、まずは子どもの“やる気スイッチ”を入れることが大切です。
ここでは、勉強が捗らない主な理由を見ていきましょう。
そもそも開始ができない
「勉強しなきゃ」という気持ちがあっても、いざ始めようとすると遊びやゲームの方が気になってしまう子は少なくありません。
楽しいことに夢中になると、気づけば勉強がそっちのけになってしまうこともあります。
そんな場合は、先に勉強を済ませてから遊ぶ習慣をつけるのがポイントです。
また、勉強する習慣や環境が整っていないことも原因のひとつ。
兄弟が近くで騒いでいたり、毎日のスケジュールに「勉強タイム」が決まっていなかったりすると、自ら勉強を始めるのは難しくなります。
集中できる環境を整え、家族みんなで協力して「今は勉強の時間」と区切ることが、最初の一歩です。
集中力が続かない
子どもは大人に比べて長時間の集中が難しく、低学年なら30分、高学年でも45分が目安といわれています。
無理に長時間勉強を続けようとすると、かえって効率が下がってしまうことも。
適度に休憩を挟みながら取り組むことが大切です。
また、勉強部屋に漫画やゲームなど気を散らすものがあると、集中が途切れやすくなります。
勉強に必要なものだけを手元に置き、集中できる環境を整えるようにしましょう。
苦手な教科を避けてしまう
誰にでも得意・不得意はあるもの。
子どもにとって苦手な教科は「どうせできない」「やっても良い点は取れない」と感じやすく、つい後回しにしてしまいます。
苦手を避け続けると、学習のバランスが崩れてしまい、さらに苦手意識が強まる悪循環に入ってしまいます。
重要なのは「小さな成功体験」を積み重ねること。
難しい問題からではなく、解けそうなところや基礎的な問題から取り組むことで、「できた!」という気持ちが次につながります。
インプット(教科書や参考書を読む)とアウトプット(実際に問題を解く)を交互に行うのも効果的です。
少しずつ前に進むことで、苦手な教科も「やればできる」に変わっていきます。
「そもそも開始できない」場合の勉強法

ゲームに夢中でなかなか勉強を始めない子どもに、「そろそろ宿題しなさい」と声をかけるけれど動かない……。
ついイライラして叱ってしまう、そんなやり取りはどこの家庭でもよくある光景です。
「毎日言い続けるだけで疲れてしまった」と感じている保護者の方も多いのではないでしょうか。
ここでは、そもそも始めない子どもにはどうすればよいのか、具体的な勉強法を紹介します。
スモールステップ法
スモールステップ法とは、大きな目標をいきなり達成しようとするのではなく、小さな段階に分けて少しずつ取り組んでいく方法です。
一つひとつを着実にクリアしていくことで達成感が積み重なり、最終的に大きな目標にたどり着けます。
やり方はとてもシンプルです。
まず、「どこまでできるようになりたいか」という最終的な目標を決めましょう。
次に、その目標を小さく分けて「漢字を5つ覚える」「算数プリントを1枚やる」といった達成しやすいステップを作ります。
大切なのは、子どもが「これならできそう」と思えるくらいの小さなゴールにすることです。
集中できる勉強環境(場所)の用意
子どもが勉強を始められない原因のひとつに、「周りに気が散るものがある」ことがあげられます。
テレビがついていたり、机のそばに漫画やゲームが置いてあったり、手元にスマホがあると、どうしても気を取られてしまいます。
勉強するときは、今使う教材やノート、筆記用具だけに絞り、他のものは見えない場所に片づけましょう。
机の横に気をそらすものが多い場合は、カバーをかけたり、別の部屋に移すのもよいでしょう。
家族も「この時間は静かにしてあげよう」と協力すれば、子どもが自然と集中モードに入りやすくなります。
「集中力が続かない」場合の勉強法
「さっきまでやる気満々だったのに、気づけば鉛筆が止まっている」――そんな経験はありませんか?
子どもの集中力は長く続かないもの。
だからこそ、ちょっとした工夫で勉強の効率を大きく上げられます。
ここでは、集中力が途切れやすい子どもにおすすめの勉強法を紹介します。
ポモドーロ・テクニック
集中力が長く続かない子どもにおすすめなのが「ポモドーロ・テクニック」です。
ポモドーロ・テクニックとは、25分勉強して5分休憩するサイクルを繰り返す方法。
短い時間に区切ることで「あと少しなら頑張れる」と思いやすく、集中力が保ちやすくなります。
時間を計るのは、キッチンタイマーがおすすめです。
スマホを使用するのは、誘惑が多いため避けましょう。
タイマーが鳴ったら勉強を中断して休憩に入り、時間が来たらまた再開。
親子で一緒に「25分集中」を実践するのも有効です。
休憩中は、おやつを食べたり体を伸ばしたり、気分をリフレッシュできることをします。
ダラダラと長時間勉強するよりも、区切りをつけて取り組むことで効率が格段に上がります。
自分へのご褒美となるルールを設定する
集中力を切らさないためには、「やった分だけいいことがある」という仕組みをつくることが大切です。
そうすることで子どもは勉強を「やらされるもの」ではなく、「やったら楽しいことにつながるもの」と感じやすくなります。
例えば「30分勉強したらシールを1枚貼れる」「プリントを解き終えたら好きなおやつを選べる」「1時間集中できたら10分だけゲームをしていい」など、子どもにとって楽しみになるルールを設定してみましょう。
ポイントは、子どもが無理なく続けられる範囲にすることです。
こうした小さな喜びを積み重ねていくことで、勉強を続けるモチベーションが生まれていきます。
「苦手な教科を避けてしまう」場合の勉強法
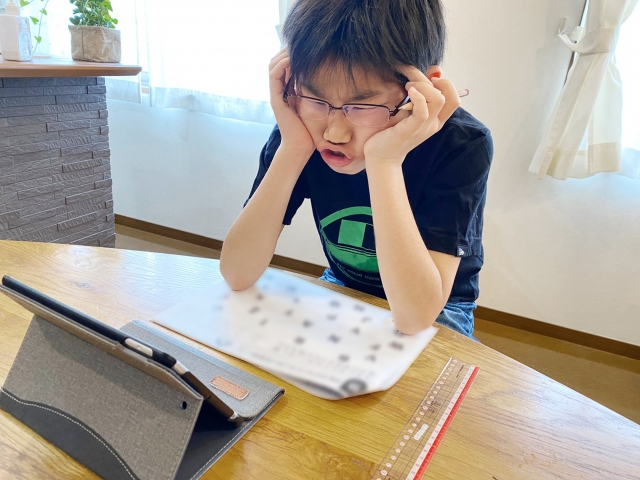
「国語は好きだけど算数はイヤ…」など、子どもにはどうしても得意・不得意があります。
苦手な教科になると気が重くなり、机に向かうのも嫌になってしまうもの。
しかし、やり方ひとつで「できない」が「ちょっと分かる」に変わり、少しずつ自信を持てるようになります。
ここでは、苦手な教科を避けずに取り組むための勉強法を紹介します。
情報収集(インプット)と問題を解く(アウトプット)の組み合わせ
苦手な教科への対策は、インプット(知識を取り入れる)とアウトプット(実際に使ってみる)を交互に繰り返すのが効果的です。
例えば算数の場合は、解き方を動画や参考書で確認してから、すぐに似た問題を1問解いてみる。
英語なら、新しい単語を覚えたらすぐにその単語を使って短い文を書いてみる。
このように「学んだことをすぐ使う」流れを作ると、理解が定着しやすくなります。
インプットだけ、アウトプットだけに偏らず、両方をセットで行うことが、苦手教科を克服する近道になります。
簡単なところから解いていく
苦手な教科に取り組むときに、いきなり難しい問題に挑戦するとと気持ちが折れてしまいがちです。
まずは、基礎的な問題や子どもが「これならできる」と思えるレベルから始めましょう。
例えば、算数なら計算ドリルの簡単な問題から、国語なら知っている漢字を使った短い文章づくりから始めるのがおすすめです。
小さな成功を積み重ねることで自信が育ち、少しずつ難しい問題にも挑戦できるようになります。
解ける感覚を増やしていくことが、苦手科目を避けずに取り組むための大事なステップです。
勉強の効率を下げるNG行動
せっかく勉強していても、知らず知らずのうちに効率を下げてしまう行動をとっていることも。
習慣になっていると気づきにくいですが、ちょっとした環境や行動のクセが集中を妨げているのです。
ここでは、勉強の効果を低下させてしまうNG行動を紹介します。
手の届く場所にスマホを置いてしまう
スマホを机の上に置いた状態で勉強するのはやめましょう。
通知が鳴ったり気になったりして集中が途切れてしまいます。
特に、YouTubeやSNSなどは「ちょっと見るだけ」のつもりが、いつの間にか1時間、2時間とどんどん時間が過ぎてしまいます。
勉強するときは、スマホを机の上やポケットに入れず、思い切って別の部屋に置いておくのが1番です。
どうしても手元に置いておきたい場合は、通知をオフにしたりアプリを一時的に制限する機能を使ったりすると集中しやすくなります。
無理のし過ぎ(疲労や睡眠不足)
夜更かしして勉強するなど、無理を重ねてしまうと集中力や記憶力は下がり、かえって効率が悪くなります。
研究によれば、小学生が1日に9時間未満の睡眠しか得られない場合、注意力や学業成績の低下リスクが高まる傾向があることが明らかになっています。
短時間の勉強を積み重ねる方が成果につながりやすいため、生活リズムを整え、十分な睡眠を確保するようにしましょう。
勉強しただけで問題を解かない・振り返りをしない
教科書を読んだりノートをまとめたりしただけで終わってしまうと、「分かったつもり」で終わってしまいます。
知識はインプットしただけでは定着せず、実際に問題を解いてみてやっと理解できるようになります。
また、解いた問題をそのままにせず、間違えたところを振り返ることも大切です。
同じミスを繰り返さないようにすることで、学んだ内容がしっかり自分のものになります。
勉強の時間の中に「振り返りの数分」を取り入れるだけで、成果はぐっと変わってきます。
まとめ
子どもが勉強を嫌がるのは、やる気がないからではなく、始めにくさや集中の難しさ、苦手意識など、いくつかの理由があるからです。
その原因に合わせて工夫をすれば、勉強はぐんと取り組みやすくなります。
スモールステップで小さな成功を積み重ねたり、集中できる環境を整えたり、時間を区切って勉強に向かうようにするなど、家庭でできる工夫はたくさんあります。
特別な準備をする必要はなく、今すぐに始められることばかりです。
勉強を「辛いもの」から「やればできる、ちょっと楽しいもの」へと変えていくことが、子どものやる気を引き出す第一歩。
日々の小さなアイデアが積み重なれば、自然と勉強が習慣になっていきます。
関連するコラム
習い事を検索
-
- (428件)
-
-
-
-
-
-









