子どもの暗算を伸ばすには?苦手意識をなくす練習法とコツ

「暗算ができないと勉強についていけないのでは…。」と心配になる保護者も多いのではないでしょうか。暗算は、正しいステップで取り組めば誰でも伸ばせる力です。
本記事では、暗算力がもたらすメリットや、学習の基本ステップ、おすすめの学習法をご紹介します。具体的な練習法や年齢別のアプローチ方法、よくある質問も含めて、実践的な内容をお伝えしていくので、ぜひ参考にしてください。
暗算力が子どもにもたらすメリット
まず初めに、暗算を身につけることで得られるメリットをご紹介します。
算数の速度が上がる
暗算力が高まると、計算問題を解くスピードが向上します。その結果、テストで問題を解く際の時間に余裕ができ、見直しの時間をしっかり取れるようになります。特に、中学受験や高校受験を見据えている場合、暗算力がもたらす時間的余裕は非常に重要です。
計算が速いと算数に前向きに取り組めるようになり、「できる!」という感覚が身につきます。こうした成功体験を積み重ねることによって、算数だけでなく、勉強全体への意欲を高める効果もあるでしょう。
集中力や記憶力の強化
暗算は頭の中で数を保持しながら処理する作業です。そのため、ワーキングメモリと呼ばれる短期記憶が継続的に刺激されることになります。ワーキングメモリは、複数の情報を同時に処理する際に欠かせない認知機能です。
ワーキングメモリが鍛えられることにより、集中力が高まりやすくなるといったメリットがあります。その結果、学校の授業で先生の説明を最後まで聞けるようになったり、長い文章問題でも途中で内容を忘れずに読み切れるようになったりします。
さらに、暗算を繰り返すことで計算力そのものが着実に磨かれていきます。繰り返し練習することで計算の正確さとスピードが向上し、数字に対する抵抗感が減っていくのです。
思考力と自信の育成
数字を組み合わせて解を導く暗算は、論理的な思考力のトレーニングでもあります。「10に分けて考える」「大きい数から引いてみる」「5を基準にして考える」といった様々な工夫を重ねることで、子どもの思考力が育まれるのです。
また、難しい問題を自分の力で解けたとき、子どもは大きな達成感を味わいます。そうした成功体験が自信につながっていきます。
暗算の基本ステップと学習法
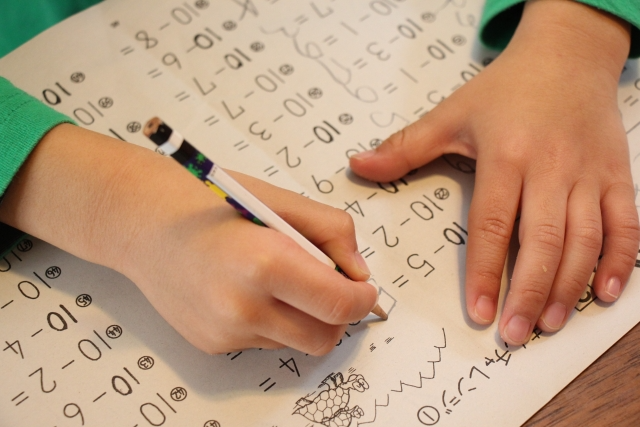
暗算は段階を踏んで学習することが大切です。ここでは、暗算の基礎から応用へと進む学習法をご紹介します。
繰り上がりのない簡単な計算から
最初のステップは、「1桁のたし算・ひき算」など、繰り上がりのない計算です。例えば、「3+4」や「8−2」、「9−3」のような計算問題です。問題をみたら答えがパッと頭に浮かぶまで繰り返し練習しましょう。お風呂の中や車での移動中など、リラックスした環境で「3+5は?」と声をかけてみるのも効果的です。
繰り上がりのない簡単な計算にスムーズに答えられるようになれば、暗算への抵抗感が大幅に少なくなります。また、基礎をしっかり固めておくことで、発展した計算にもスムーズに進んでいくことができます。
繰り上がり・繰り下がりの計算
次に取り組むのは、「9+7」や「13−9」、「8+5」といった繰り上がり・繰り下がりを伴う計算です。この計算は、多くの子どもにとって、最初の大きな壁となることが多いでしょう。
繰り上がり・繰り下がりの計算では、「10を作る」という考え方を導入すると効果的です。「8+5」なら「8+2+3」と分解し、「(8+2)+3=10+3=13」と考える方法です。頭の中でイメージできるようになるまで繰り返しましょう。
大きな桁数の暗算テクニック
基礎が固まってきたら、「27+36」や「85−47」、「64+28」などの2桁の暗算に挑戦します。この段階では、「十の位と一の位を分けて考える」といった工夫が役立つでしょう。
例えば、27+36なら「20+30=50」と「7+6=13」を計算し、最後に「50+13=63」とまとめる流れです。引き算の場合も同様に、「85−47」なら「80−40=40」と「5−7」を考え、一の位で足りない分を十の位から借りてくる操作を頭の中で行っていきます。
数を分解して整理する習慣がつくと、暗算の効率がぐんと上がっていきます。さらに上達すれば、3桁の計算などを暗算でできるようになるでしょう。
暗算力を育む具体的な練習法
子どもの暗算力を育てるには、机に向かった勉強だけでなく日常の中で練習できる工夫が大切です。ここでは、暗算力を育む具体的な練習法をご紹介します。
最初は指を使って計算
指を使って計算することで、数の感覚をより確実につかみやすくなります。そのため、暗算がまだ難しい段階では、指を頼って計算しましょう。
指を使って正確に計算できるようになったら、徐々に指に頼る頻度を減らしていけば、自然と頭の中だけで計算できるようになります。一方で、無理に指を禁止してしまうと、かえって計算への恐怖心を植え付けてしまう可能性があるため注意が必要でしょう。
10のまとまりを作る練習法
「10になる組み合わせ」を瞬時に思い浮かべられるようになると、暗算がぐんとスムーズになっていきます。例えば、「8+2」「7+3」「6+4」「9+1」などの組み合わせです。
親子で、「どんな組み合わせで10になる?」とクイズ形式で練習する方法がおすすめです。また、ランダムに数字を言って、「10にするには何を足せばいい?」と問いかけるゲームも効果的でしょう。遊びながら学ぶことで、暗算への苦手意識がやわらぎ、楽しいこととして捉えられるようになります。
慣れてきたら、「20になる組み合わせ」や「100になる組み合わせ」にも挑戦してみると良いでしょう。
数字の分解と合体を使った練習法
数を分解したり組み合わせたりすることで、頭の中の数のイメージが格段に広がっていきます。例えば、「9+6」を「9+1+5=10+5=15」や「10+5」に変えて考える方法です。また、「8+7」なら「8+2+5=10+5=15」というように工夫することもできるでしょう。
数字の分解と合体を使った練習法は、算数だけでなく、物事を多角的に捉える力にもつながっていきます。「一つの答えにたどり着くまでに、いくつもの道筋がある」ということを実感できるため、創造性の育成にも役立つのです。
親子で、「どうやったらもっと簡単に計算できるかな?」と話し合いながら練習すると効果的でしょう。子ども自身がアイデアを出すことで、より深い理解につながっていきます。
日常生活での活用(買い物のお釣りなど)
生活の中で実際に暗算を使う場面を意識的に作りましょう。お釣りを考えたり、時間を計算したり、料理の量を考えたりすることは、子どもにとって実感を伴った学びになります。
時計を見ながら、「あと30分で出発だけど、準備にどのくらいかかるかな?」と時間の計算を促すのも計算の練習になります。このような実用性を感じられる経験が、学習への動機を高める重要な要素になるでしょう。
ゲーム感覚の取り組み方
ゲーム要素を取り入れた暗算練習も非常に効果的です。家族で、「10秒以内に答えられるかな?」といった暗算競争をしたり、問題の正解数によってポイントを貯めたりする仕組みを作ることで、子どもの意欲が格段に高まるでしょう。
また、車での移動中に車のナンバープレートを使った足し算ゲームや、買い物中に商品の合計金額を計算するゲームなど、日常生活にゲームを取り入れるのも効果的です。勉強しているという意識をせずに楽しく取り組めるため、継続しやすいのが大きなメリットです。
効率的な暗算トレーニングの手段

暗算をさらに強化するには、ツールや教材をうまく活用することも有効です。ここでは、効率的な暗算トレーニングの手段をご紹介します。
アプリ・ゲームでトレーニング
スマホやタブレットには、暗算力を鍛えるアプリが多数存在しています。「そろばん」「暗算トレーニング」「計算ゲーム」といったキーワードで検索すると、様々な選択肢が見つかるでしょう。ゲームのようにスコアを競う形式だと、子どもも楽しみながらトレーニングができます。
ただし使いすぎには注意が必要です。1日10〜15分程度を目安に、短時間で効果的に取り入れると良いでしょう。デジタル機器の使用については、事前に親子でルールを決めて取り組むことが大切です。
そろばんでトレーニング
そろばんは暗算力を伸ばす強力なツールです。珠をイメージする「珠算式暗算」は、数字を頭に思い浮かべて処理する力を効果的に鍛えてくれます。指を動かすリズムも心地よく、集中力が持続しやすいのが特徴です。
そろばんは段階的に難易度を上げられることと、正確性を重視した練習ができることがポイントです。検定試験など、目標があることで継続的な学習の動機にもなるでしょう。習い事として始めるのはもちろん、家庭で簡単な練習を取り入れるだけでも十分効果がありますよ。最近では、オンラインでそろばんを学べるサービスも増えているため、通塾が難しい場合でも取り組みやすくなっています。
年齢別のアプローチ方法
幼稚園年長〜小学1年生の時期は、数の概念をしっかりと理解することが最優先です。おはじきや積み木などの具体物を使いながら、「数を見る・触る・動かす」経験を重ねていきましょう。この時期に無理をして暗算をトレーニングする必要はありません。
小学2〜3年生になったら、1桁の暗算を中心に練習していきます。繰り上がり・繰り下がりの概念をゆっくりと身につけ、確実にできるようになってから次のステップに進むことが大切です。
小学4年生以降は、2桁の計算や簡単なかけ算の暗算にも挑戦できるようになります。ただし、個人差が大きい時期でもあるため、子どもの様子を見ながら調整していくことが重要でしょう。
子どもの暗算に関するよくある質問
暗算の大切さはわかっても、実際の家庭学習では様々な悩みが出てきます。最後に、多くの保護者が疑問に思うポイントを具体的に解説していきます。
なんで暗算は大切なの?
暗算は計算の速さだけでなく、考える力を総合的に伸ばすトレーニングです。頭の中で数を操作することで、記憶力や集中力、そして論理的思考力も同時に養われていきます。これらの能力は、算数以外の教科や将来の学習においても思考の重要な基盤となるため、暗算力を身につけておくことが大切なのです。
子どもが集中してくれません。どうすればいいですか?
子どもの集中力が続かないのは自然なことです。まずは、短時間で区切って取り組むのがおすすめです。最初は3〜5分間だけ取り組み、慣れてきたら徐々に時間を延ばしていく方法が効果的でしょう。
一方で、子どもが「もうやりたくない」と言ったときは、無理強いせずに一度休憩を取ることも大切です。嫌な気持ちのまま続けても効果が上がらないため、子どものペースに合わせて練習を進めましょう。
電卓やスマホがあるのに、暗算は必要ですか?
暗算は計算力だけでなく、思考力を鍛える重要な手段です。確かに、電卓やスマホがあれば複雑な計算も簡単にできます。ただ、デジタル時代だからこそ、自分の頭で考える力の重要性は増しているといえるでしょう。暗算で鍛えられた思考力は、大人になってからも役立つため、子どものうちにしっかりと育てておくことが大切なのです。
まとめ
暗算力は算数だけでなく、集中力や記憶力、そして自信を育む大切な力です。基礎から少しずつステップを踏み、日常生活に自然に取り入れながら練習していけば、子どもの暗算力は確実に伸ばせます。
アプリやそろばんなどのツールを活用するのも効果的です。また、ゲーム感覚で楽しく取り組めるような工夫をすることで、暗算のトレー二ングを継続しやすくなります。
暗算が、苦手から得意に変わると、学習全体にポジティブな変化が生まれていくものです。今回ご紹介した方法を取り入れて、子どもの暗算力をサポートしていきましょう。
関連するコラム
習い事を検索
-
- (428件)
-
-
-
-
-
-









