足し算が得意になる!子どもが楽しく学ぶポイント

小さな子どもに足し算を教えようとしても、「どうやったら分かりやすく伝えられるかな?」と迷うことはありませんか?
大人にとっては簡単な計算でも、初めて学ぶ子どもにとっては未知の世界。
だからこそ、正しい理解につながる教え方や工夫が大切です。
この記事では、足し算の基本的な教え方から、楽しく学べる練習法、幼児期に取り入れたいポイントまで分かりやすく解説します。
未就学児や小学校低学年のお子さんを持つ方、これから教育に力を入れたい方は、ぜひ参考にしてください。
なぜ足し算は算数の基本なのか
足し算は算数の出発点で、続く引き算・掛け算・割り算などすべての計算の基礎となるものです。
計算の流れを理解するための“入口”であり、ここでつまずくと算数全体への苦手意識につながってしまいます。
だからこそ、最初にしっかりと土台を築くことが重要です。
足し算の概念と重要性
足し算は、2つ以上の数を合わせて合計を求める計算です。
子どもに教えるときは、単純に数字を並べて計算するだけではなく、「何を合わせるのか」という意味づけを理解させることが大切です。
発明王エジソンが小学生だった頃、「1+1=2」に疑問を持ったという有名な逸話があります。
エジソン少年は、「1つの粘土と1つの粘土を合わせたら、大きな1つの粘土になる。だから1+1=1じゃないの?」と考えたのです。
聞かれた先生は困ってしまったそうです。
ですが、この疑問は「粘土1kg+粘土1kg=粘土2kg」のように、単位をつけて意味を持たせれば解決できます。
算数では、単位や意味を理解せずに数を数字だけで捉えると、頭が混乱してしまいます。
例えば、部屋番号の104、身長157cm、お菓子の値段34円を足し合わせても、何の意味もありません。
大切なのは、「何を求めたいのか」を意識し、その目的に沿った数だけを足すことです。
ここで身につけた感覚は、様々な計算の基礎となり、日常生活や将来の学びでも大いに役立ちます。
つまずきやすいポイントと原因
足し算で特につまずきやすいのが「繰り上がり」です。
繰り上がりとは、「7+4」や「8+6」のように、一の位の合計が10を超えて十の位に1を加える計算のこと。
小学校低学年の算数で最初に訪れる大きなハードルともいえます。
繰り上がりがある計算では、「まず10を作る」→「残りの数を足して…」という複数のステップが必要になります。
そのため、反射的に答えられず、途中で混乱してしまう子が多いのです。
さらに、苦手なままやみくもにドリルを解いても、なかなか定着はできません。
重要なのは、繰り上がりの手順や考え方をしっかり意識しながら解き進める練習を積むこと。
これにより、繰り上がりの壁をスムーズに越えられるようになります。
足し算の基本ステップを理解する

足し算は、基本ステップを理解することから始めましょう。
ここでは、どのように学習していけばよいか解説します。
「合わせていくつ?」から始める
まず足し算を理解するうえで大切なのは、「合わせていくつ?」という感覚を身につけることです。
数字だけで計算式を見せるのではなく、まずは身近なものを使って、数量が増える様子を体験させてあげましょう。
例えば、おはじきやブロックを使って「3個あります。そこに2個足すと、合わせていくつになるかな?」と問いかけます。
実際に手で動かしながら数えることで、「数を合わせる=足し算」という意味が自然と理解できます。
この段階では、まだ式や記号にこだわらず、具体物を動かしながら「増える」「合わせる」という経験をたくさん積ませることが大切です。
こうして感覚を育てておくと、次の段階で数字や記号を使った計算にスムーズに移行できます。
繰り上がりのない足し算
足し算に慣れるための次のステップは、繰り上がりのない足し算です。
これは「2+3」や「4+5」のように、一の位の合計が10未満で収まる計算のことです。
思考の流れがシンプルで、答えを導くまでのステップが1つだけなので、足し算の基礎固めに最適です。
この段階では、具体物や指を使って数える方法を繰り返すことで、「数の合計を求める」感覚を強化しましょう。
また、答えを声に出しながら数えることで、記憶の定着も促されます。
繰り上がりのある足し算
繰り上がりのない足し算に慣れたら、次は繰り上がりのある足し算に進みましょう。
これは「7+4」や「8+6」のように、一の位の合計が10を超える計算のことです。
前述の通り、繰り上がりの計算は「まず10を作る」→「残りの数を足して…」といった、複数の思考ステップが必要になります。
スムーズに解けるようになるには、10を基準にして数を分ける練習が効果的です。
ブロックやおはじきなどを使い、「まず10を作る」体験を繰り返すことで、繰り上がりの感覚が自然と身につきます。
こうして練習することで、二桁や三桁の計算にも対応できる計算力が育ちますよ。
子どもの力を引き出す練習方法
ここでは、子供の力を引き出すのにおすすめの練習方法を3つ紹介します。
足し算に苦手意識を持ってしまう前に、ぜひ実践してみてください。
具体物を使った計算練習
1つ目に紹介するのは、具体物を使った計算練習です。
まずは机の上に、おはじきを3つ並べます。
「ここにもう2つ置いたら、全部でいくつになる?」そう問いかけると、子どもは指で一つひとつ数えながら答えを探します
数字だけではつかみにくかった“数が増える感覚”が、形になります。
使うのは、おはじきでも、ブロックでも、飴玉でも構いません。
ただし、形や大きさがそろっているほうが、数のまとまりが見やすくなります。
さらに、玉そろばんや知育玩具、足し算ポスターなども取り入れれば、遊びの延長で学べる時間に早変わり。
指先を動かし、目で数を確かめる経験が、計算を“頭だけの作業”から“実感できる学び”へと変えてくれます。
数図ブロックや数直線の活用
2つ目に紹介するのは、数図ブロックや数直線の活用です。
数図ブロックは、数字の大きさを色や長さで表した教材です。
1〜10までのブロックを組み合わせることで、足し算の結果が視覚的にわかります。
例えば「5+3」であれば、5のブロックと3のブロックを並べると、長さが8のブロックと一致するため、答えを一目で確認できます。
数字の大小や合計の感覚をつかみやすく、繰り上がりのある計算の理解にも役立ちます。
数直線は、数字を一定間隔で並べた線上を移動しながら計算する方法です。
「7から4進むとどこに着く?」という形で、スタート位置から右に進めば足し算、左に進めば引き算になります。
目盛りを数えながら進むため、計算の流れを視覚的に確認でき、暗算の基礎づくりにもつながります。
暗算力を高めるゲーム
暗算力を伸ばすには、机に向かって計算問題を解くよりも、遊びの中で数を扱う経験が効果的です。
暗算力は10歳までの計算トレーニングで高められます。
今では、脳トレ計算アプリや数字に強くなるアプリが無料で入れられます。
ゲームを活用して、繰り返し計算練習することで、暗算力は高められます。
日常生活で足し算に触れる
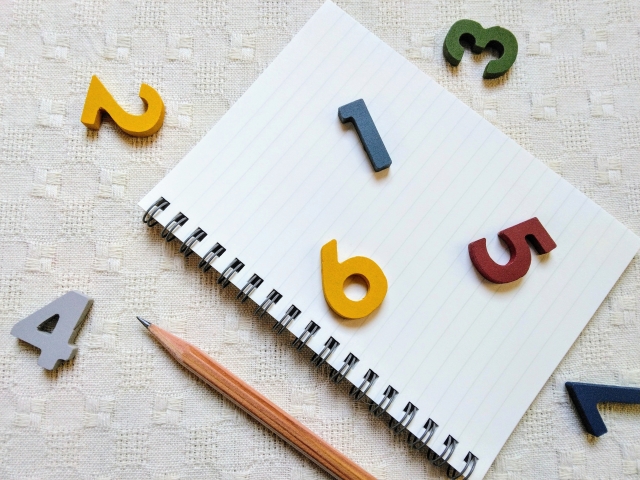
買い物での金額の合計や、お菓子の数を数えるとき、友だちや家族の人数を数えるときなど、日常のあらゆる場面で足し算は使われています。
こうした生活の中で「足し算って便利だな」と感じられる経験を積むことで、理解が深まります。
遊びの中での計算体験
まずは先ほどご紹介したように、おはじきや積み木、ブロックやボールなど、同じ形のおもちゃを使って「合わせて何個になる?」と問いかけることで、初歩の足し算を体験させましょう。
大切なのは、子どもがすぐに答えられたからといって急に数を増やさないことです。
難易度を上げすぎると混乱しやすくなるため、少ない数で繰り返し練習し、確実に理解を深めていくことがポイントです。
慣れてきたら、おもちゃからトランプやサイコロなど、数字が書かれた道具にステップアップすると、より算数らしくなっていきます。
お手伝いで足し算の場面を作る
足し算は、日常のお手伝いの中でも身につけられます。
例えば夕食の準備で、「みんなの分のお皿を並べてくれる?」と頼むと、子どもは家族の人数とお皿の数を自然に結びつけます。「あとパパの分とママの分を足して…」と、まるでパズルのピースをそろえるように数を揃えていくのです。
お菓子を買うときも絶好のチャンスです。
「3個までなら好きなのを選んでいいよ」と伝えると、子どもは数を意識しながら選びます。
「2個入れたから、あと1個だね」というやりとりは、子どもにとっては、まるで宝探しの最後の1ピースを見つけるようなわくわく感があるのです。
そうすることで、計算を「勉強」ではなく「生活の中の一部」として体験できるため、数字への苦手意識を減らせます。
絵本や歌で楽しく学ぶ
足し算は、机に向かう練習だけでなく、絵本や歌を通しても楽しく身につけられます。
「1+1=2、1+2=3」といった小さな数同士の足し算にメロディをつけて歌えば、自然とリズムにのって覚えられます。
耳から入る情報は記憶に残りやすく、未就学児でも無理なく答えを覚えられるのが魅力です。
また、足し算をテーマにした絵本は、ストーリーの中で数が増えていく様子を視覚的に理解できます。
動物が集まっていく場面や、お菓子が増えるシーンなど、ページをめくるごとに「合わせていくつ?」と問いかければ、計算が物語の一部になります。
パソコンやスマートフォンで足し算の歌を再生し、親子で一緒に歌ったり、絵本を読みながら声に出して数える時間を作ることで、遊びと学びが自然につながっていきます。
アプリを活用する
スマートフォンやタブレット向けの学習アプリを活用すれば、遊び感覚で足し算を練習できます。
カラフルなイラストやアニメーション、効果音がついた問題は、子どもの集中力を引き出しやすく、繰り返しの学習も飽きにくいのが特徴です。
足し算に特化したアプリでは、正解するとキャラクターが褒めてくれたり、ポイントが貯まってご褒美が貰えたりするなど、達成感を得られる仕組みが用意されています。
これにより、「もっとやりたい!」という意欲が自然に高まります。
アプリを選ぶ際は、子どもの年齢やレベルに合った内容か、広告や課金要素が少なく安全に使えるかを確認しましょう。
短時間でも毎日続けることで、足し算の基礎がしっかりと身につきます。
まとめ
足し算は、これから学ぶ算数の基礎となる大切な力です。
まずは、「合わせていくつ?」という感覚をおもちゃやおはじきなどを使って身につけましょう。
それに慣れてきたら、繰り上がりのない計算 → 繰り上がりのある計算へと順を追って進めることで、混乱を減らしスムーズにレベルアップできます。
日常生活の中でも、お手伝いや買い物、遊びを通して自然に足し算に触れる機会を作ることがポイントです。
絵本や歌、学習アプリなども取り入れれば、より楽しく学ぶことができます。
小さな成功体験を積み重ねながら、数字を身近で親しみやすい存在にしていくことが、足し算を得意にする近道です。
日常の中でさりげなく足し算に触れられるよう、楽しいきっかけをつくってあげましょう。
関連するコラム
習い事を検索
-
- (428件)
-
-
-
-
-
-









