分数が得意に!子どもが自信をもてる学習法
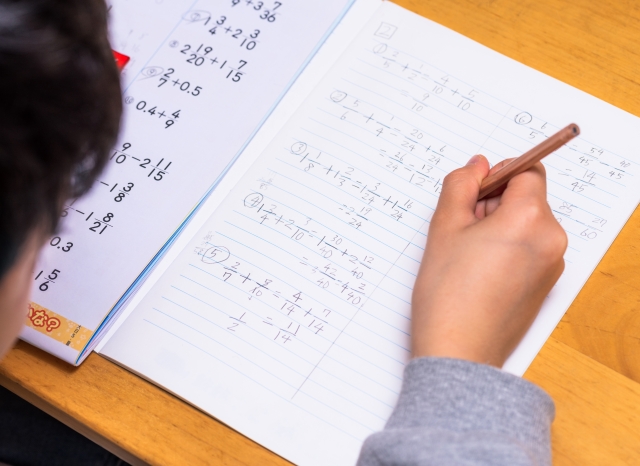
分数は、多くの子どもがつまずきやすい算数の単元です。整数や小数とは違った考え方が必要で、複雑に感じてしまうためです。分数を習い始めて、算数全体に苦手意識を持ってしまう子どもも少なくありません。
でも実は、分数は日常生活でもよく使われる身近な数学。しっかり理解することで、算数全体への自信につながり、その後の数学学習の土台になります。
この記事では、分数が難しく感じる理由や基本的な概念の理解、段階的な計算方法の習得、そして楽しく学べる具体的な方法を解説します。
なぜ分数でつまずきやすいのか
まずは、子どもがなぜ分数でつまずきやすいのか、分数が苦手になりやすい理由を3つの観点から見ていきましょう。
分数の概念が難しい
分数は「1つのものをいくつかに分けた中の、いくつ分か」を表します。1、2、3…と順番に数える整数とは異なる考え方で、全体と部分の関係という抽象的な概念が必要です。
特に、低学年の子どもにとって、見えないものを分けるというイメージは難しいものです。例えば、1/4がどのくらいの大きさなのかは頭の中でイメージしにくく、実際にケーキやピザを4等分して1つ取ってみないと分からないものです。
また、分子や分母といった、新しい専門用語が増えることも分数でつまずきやすい要因の一つです。「分子って何?」「なぜ上と下で呼び方が違うの?」といった疑問が、分数という概念の理解を妨げることもあります。
さらに、分数は部分を表す数であると同時に、割り算の結果でもあるという二面性があります。そういった複雑さも、分数の理解を困難にしているのです。
小数や整数との違いにとまどってしまう
整数は、1、2、3…と順番に数えるだけの単純な仕組みです。しかし、分数は一つのものを分けて数えるため、数の大小関係が直感と正反対になることがあります。
最もわかりやすい例が、1/2と1/3の大小関係です。ぱっと見ると、「3の方が2より大きいから、1/3の方が大きい」と思ってしまいがちですが、実際は1/2の方が大きいですよね。
さらに複雑に感じやすいのが、分数と小数の関係です。1/2=0.5、1/4=0.25など、同じ数なのに表記が異なることで、混乱が生じます。
計算方法が難しい
分数の計算は、整数計算とは全く異なる手順が必要です。通分、約分、逆数など、これまでになかった新しい概念と技術を同時に習得しなければなりません。このような計算方法の難しさが、分数でつまずきやすい要因の一つとなっています。
分数の足し算・引き算では、まず分母をそろえる「通分」が必要です。通分では、最小公倍数を求める技術も必要で、一つの計算の中に複数のステップが含まれています。一方、掛け算・割り算では、分子同士、分母同士を掛けたり、割る数を逆数にして掛けたりといった、全く異なる手順が必要になり、子どもは混乱してしまいます。
また、計算の手順を覚えたとしても、根本的な概念を理解しないまま進んでしまうことがよくあります。その結果、機械的に計算はできても、理屈が分からないため応用が利かず、問題が少し変わると対応できません。こういった計算方法の複雑さが理由で、子どもが分数を難しく感じてしまうのです。
分数の基本

分数を確実に理解するには、まず基礎をしっかりと固めることが重要です。まずは、分数とは何か、どんな種類があるのかという基本的な内容を知っておきましょう。
分数とは
分数とは、「1つのものを同じ大きさに分けて、その一部を表す数」です。分数の構造を理解するポイントは、分母が「全体をいくつに分けたか」を表し、分子が「そのうちのいくつ分を取ったか」を表すということです。間にある横線は、分けるという意味を持っています。
例えば、1/4は「1つを4等分したうちの1つ分」という意味です。ここで重要なのは、分母が大きくなるほど1つ分は小さくなり、分子が大きくなるほど全体としての量が多くなるという関係性です。
また、分数は割り算の結果を表すことができます。例えば、3÷4=3/4というように、割り切れない割り算の答えを分数で表現することができるのです。この考え方は、小数との関係を理解する際にも重要になります。
3つの種類(真分数・仮分数・帯分数)
分数には、表現方法によって3つの種類(真分数・仮分数・帯分数)があり、それぞれに特徴と使い分けがあります。
まず、真分数は2/5や3/7のような、分子が分母より小さい分数です。1未満の数を表し、「全体の一部」を示します。日常生活でよく使われる形で、直感的に理解しやすく、グラフや図で表現する際にも扱いやすい形の分数です。
次に、仮分数は7/4や8/3、5/5のような、分子が分母より大きいか等しい分数です。1以上の数を表し、「全体を超える量」を示します。計算では扱いやすいのですが、量感をつかみにくい場合があります。一方で、数学的な処理では重要な形の分数です。
そして、帯分数は1と3/4や2と1/3のような、整数部分と真分数部分を組み合わせた分数です。仮分数を分かりやすく表現したもので、日常的な感覚に近いため量感をつかみやすく、測定や料理のレシピなどでよく使われます。
真分数・仮分数・帯分数は相互に変換することができ、問題や状況に応じて使い分けることが重要です。
計算方法を段階的に学ぶ
分数の計算を一度に覚えようとすると混乱が生じやすいです。そのため、まずは基本的な通分・約分をしっかりマスターし、その後で四則演算に進むという段階的なアプローチが効果的です。ここからは、計算方法を段階的に学ぶ際のステップをご紹介します。
通分と約分の理解
まずは、分数計算の基礎である通分です。通分は、異なる分母を持つ分数を、同じ分母にそろえることです。通分の手順は、まず各分数の分母の最小公倍数を求め、次に各分数をその最小公倍数を分母とする分数に変換し、分子も対応して変換します。
例えば、1/2と1/3を通分する場合、2と3の最小公倍数は6ですから、1/2は3/6に、1/3は2/6に変換します。同じ分母になることで、計算ができるようになります。最小公倍数を求めるのが難しい場合は、分母同士を掛けた数を共通分母として使うこともできますが、その場合は約分が必要になることが多いです。
約分は、分子と分母を同じ数(公約数)で割り、分数をよりシンプルな形にすることです。約分の手順は、分子と分母の公約数を見つけて、分子と分母を公約数で割り、これ以上公約数がない状態まで繰り返します。
例えば、8/12を約分する場合、8と12の公約数は4ですから、8÷4=2、12÷4=3となり、8/12=2/3となります。
最初は、小さな数で練習することが大切です。九九を活用して最小公倍数を見つける練習がおすすめです。また、円グラフなど具体的な図を用いて、通分・約分の意味を視覚化すると、より理解が深まりますよ。
分数での”足し算”・”引き算”の計算方法の理解
通分と約分が理解できたら、分数の足し算・引き算の計算方法を習得しましょう。分数の足し算・引き算では、分母が異なる場合、通分してから計算する必要があります。
分母が同じ場合は、分母をそのまま残し、分子同士を計算します。例えば、2/5 + 1/5=3/5、3/7−1/7=2/7のような計算です。比較的簡単で、子どもが理解しやすい計算です。
また、分母が異なる場合は、まず通分して分母をそろえます。次に、分母をそのまま残して分子同士を計算し、最後に必要に応じて約分が必要です。例えば、2/3−1/6の計算では、3と6の最小公倍数は6ですから、2/3を4/6に通分します。すると、4/6−1/6=3/6となり、これを約分し、計算結果は1/2となります。
さらに、帯分数を含む計算では、帯分数を仮分数に変換してから計算するか、または整数部分と分数部分を分けて計算する方法があります。最初は時間をかけても構わないので、一つ一つの手順を確実に理解することが大切です。
分数での”掛け算”・”割り算”の計算方法の理解
分数の掛け算・割り算は、足し算・引き算とは異なる考え方が必要です。しかし、手順自体は比較的シンプルであるため、理解すれば習得しやすい分野でもあります。
まず掛け算の計算では、分子同士を掛け、分母同士を掛けるだけで、通分は不要です。例えば、2/3×3/4=(2×3)/(3×4)=6/12=1/2となります。掛け算を理解するポイントは、2/3×3/4が「2/3の3/4倍」を意味するということです。全体の2/3のうち、さらにその3/4という考え方や、縦2/3、横3/4の長方形の面積といった面積の計算でイメージすることができます。
次に、割り算の計算方法では、割る数を逆数にして掛け算に変換します。例えば、2/3÷3/4=2/3×4/3=8/9となります。割り算を掛け算に変換する理由は、「3/4で割る」ことが「4/3倍する」ことと同じだからです。具体例として、6÷2=6×1/2=3を見れば、理解しやすいでしょう。
視覚と体験で分数を学ぶ

数字だけで分数を学ぶと、抽象的で難しく感じやすいものです。しかし、目で見て、実際に体験することで、子どもは分数を身近なものとして理解できるようになります。最後に、視覚と体験を使った効果的な学習方法をご紹介します。
具体物を使った分数のイメージ
具体的な物を使って分数のイメージを掴みやすくしましょう。例えば、食べ物は分数の学習に最適な教材です。実際に分けて食べることで、量として分数を体感できるためです。
また、工作材料での学習も有効です。色紙や画用紙を折ったり切ったりして分数を視覚化することで理解を助けます。ブロックで分数の組み合わせを学んだり、おはじきやビー玉を使って分数を学ぶこともできますよ。
日常生活での分数の使用
日常生活では、分数を使う場面がたくさんあります。
例えば、料理での分数活用は非常に効果的です。レシピの分量で、小さじ1/2やカップ3/4などの表現に触れたり、材料を分ける際に、お肉を3等分しようと声をかけたりします。また、食材の消費量を意識して、じゃがいもを2/3使ったから、残りは1/3だね、といったように確認することも有効です。
また、時間を分数で表現することも、身近な学習材料としておすすめです。時計の読み方で「15分=1/4時間」「30分=1/2時間」を学んだり、予定の管理で「宿題に1/3、遊びに1/3、テレビに1/3の時間を使おう」と分数を使って時間配分を考えたりできます。
これらの場面では、分数が便利な表現方法であることを強調し、分数を使うことで正確に量を表現できることを実感させることが大切です。
遊びの中での学習
遊びを通じた学習は、子どもが分数に親しめる効果的な方法の一つです。競争要素や達成感を取り入れることで、楽しく継続的に学習できますよ。
分数を活用したゲームとして、以下がおすすめです。
・分数カード合わせ:同じ値を持つ異なる表現の分数(1/2と2/4など)を組み合わせる
・分数の大小比べ:カードを引いて大きい方が勝ちと言う
・分数すごろく:マスに分数を書いて計算しながら進む
・分数パズル:円や正方形を分割したピースを組み合わせて1を作る
ゲームを活用した学習では、遊びの中で競争や協力を交えることで、自然と繰り返し学習ができる点もメリットの一つです。
また、以下のようなデジタルゲームやアプリの活用も効果的です。
・分数の視覚化アプリ
・オンラインの分数ゲーム
・タブレットを使った分数の操作体験
これらの遊びを通じて、分数が楽しいものだという印象を与えることが大切です。子どもの学習レベルに合わせて難易度を調整し、成功体験を積ませることを重視しましょう。親も一緒に楽しむ姿勢を示し、達成感を大切にすることで、より効果的に学習できますよ。
まとめ
分数は複雑な概念ですが、概念の理解・種類の把握・計算方法の習得という段階を踏んで丁寧に学ぶことで、必ず克服できる分野です。特に、目で見て体験できる学習方法を積極的に取り入れることで、抽象的だった分数が、具体的で身近なものに変わります。
重要なのは、子どもの理解度に合わせて無理をせず、一つ一つ確実に積み上げていくことです。分数でつまずく多くの原因は、基礎的な概念理解が不十分なまま計算練習に進んでしまうことにあります。時間をかけてでも、「分数とは何か」「なぜその計算方法なのか」を理解させることが、長期的な学習成功につながります。
今回ご紹介した方法を、子どもの性格や学習スタイルに合わせて選択し、ご家庭の学習に取り入れてみてください。毎日少しずつでも分数に触れる機会を作り、分数を子どもの得意分野にしてあげましょう。
関連するコラム
習い事を検索
-
- (428件)
-
-
-
-
-
-









