ギフテッドとは?特徴と才能を伸ばすために
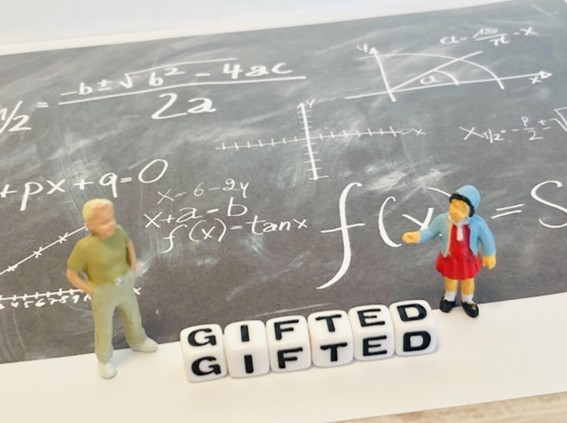
近年、ドラマや映画の題材にされることもあり、文部科学省が支援に動き出したことによって話題になっているギフテッド。
「この子、ちょっと他の子より優れているところがあるかも!?」そんな風に感じたことがあったら、ギフテッドの可能性があります。
IQが高く、何も困らないように感じるギフテッドですが、集団生活においては問題児と誤解され、学校で孤立してしまうことも。
この記事では、ギフテッドの特徴や診断方法、発達障がいとの違い、才能の伸ばし方について解説します。
ギフテッドの基本
ギフテッドとは、生まれつき特定の分野で非常に優れた能力を持つ子どものことです。
年齢相応ではない才能を見せることから、「神からの贈りもの」という意味でギフテッドと呼ばれており、日本では250万人以上いると言われています。
高いIQや学力だけでなく、芸術的な表現力や鋭い感受性、強い倫理観など、さまざまな形でその才能は現れます。
「天才」という表現が近いかもしれませんが、全般的に優秀というよりも「ある特定の分野において、能力が秀でている」ことに着目しているため、「天賦の才」という表現がより適しているかもしれません。
一見、恵まれた存在のように思えますが、周囲と違う感覚を持っているがゆえに、生きづらさや孤独を感じやすいといった、本人にしか分からない辛さがあります。
ギフテッドの定義
ギフテッドには、明確な定義は存在しません。
特にアメリカはギフテッド先進国と言われていて、さまざまな州ごとに異なる定義が採用されており、その子どもの能力や環境に応じた柔軟な捉え方がされています。
中でも多くの州で参考にされているのが、テキサス州教育法による以下の定義です。
| このサブチャプターにおいて、「ギフテッドおよびタレンテッドの生徒」とは、同年齢・同じ経験・同様の環境にある他の子どもと比較して、著しく高い達成レベルを示す、またはその可能性を持つ子どもや若者を意味します。そして、以下のいずれかの特徴を示します:知的・創造的または芸術的な分野において、高い実行能力を持つ卓越したリーダーシップ能力を有している特定の学術分野において優れている(1995年テキサス州第74議会、第260章、第1項、1995年5月30日施行) |
このようにギフテッドは、単なるIQの高さだけでなく、創造性や芸術性、リーダーシップなど多様な才能のあり方を含む広い概念とされています。
引用:https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/ED/htm/ED.29.htm
ギフテッドが生まれる理由
ギフテッドが生まれてくる理由は、まだはっきりと解明されているわけではありません。
精神科医の岩波明氏は、「遺伝の影響はあるかもしれないが、なぜギフテッドが生まれるのかは分かっていない」と述べています。
一方で、アメリカのNAGC(全米ギフテッド児協会)は、「ギフテッドは生まれつき決まるものではなく、育てられる才能だ」という考え方を示しています。
どの子も才能の“タネ”を持って生まれてきますが、それが育つかどうかは、周りの環境や関わり方次第。
つまり、ギフテッドは“特別な子が生まれる”のではなく、“良い環境の中で才能が育った結果”だといえます。
親や先生のサポート、子どもに合った学びの機会が、その子の力を大きく引き出すカギになるのです。
ギフテッドの子どもの特徴

ギフテッドの子どもは、一般的な発達とは異なる特性を持っていることがあります。
ここでは、代表的な5つの特徴を紹介します。
学習能力が高い
ギフテッドの子どもは、初めて触れる内容でも素早く理解し、自分なりに応用できる力を持っています。説明を最後まで聞かなくても流れを読み取ったり、一度見ただけの内容をすぐに覚えてしまったりすることもあります。
学校の内容では物足りなさを感じ、自分で調べてどんどん学びを広げていく姿が見られることも少なくありません。
感受性が高い
ギフテッドの子どもは感受性が高く、まわりの人の表情や声のトーン、教室の空気の変化にも敏感に気づきます。例えば、友達が少し機嫌を悪くしているだけで気にしすぎてしまったり、ニュースや映画の悲しいシーンで強く心を揺さぶられたりすることがあります。
こうした繊細さは創造性の土台になる一方で、心が疲れやすいため、ご家庭では安心できる環境を作ってあげましょう。
好奇心旺盛
「これはどうなってるの?」「なぜそうなるの?」といった疑問を次々と投げかけ、答えを探す過程そのものを楽しみます。
関心のあるテーマには驚くほど集中し、周囲が気づかないような点に目を向けることもあります。
こうした好奇心が、自ら考えて行動する「探求心」につながるケースも見られます。
記憶力が優れている
ギフテッドの子どもは、見たり聞いたりしたことを、まるで脳内で写真を撮って振り返っているかのように記憶していることがあります。
一度読んだ本の内容を細かく覚えていたり、何年も前の出来事を、そのときの会話や場所まで鮮明に思い出すことも。
大人がすっかり忘れているような細かいことまで正確に覚えていて、思わず驚かされることもあるでしょう。
論理的な考えが得意
ギフテッドの子どもは、物事の仕組みや原因を筋道立てて考える力に優れています。
「どうしてそうなるのか」「なぜそう考えたのか」と、自分なりの根拠や理由を持って行動することが多く、その思考の深さはときに大人顔負けのこともあります。
ギフテッドの診断方法
ギフテッドかどうかはご家庭での判断が難しく、検査機関で確認を行うことができます。
ここでは、代表的な診断方法をご紹介します。
WISC-Ⅳ(ウェクスラー式知能検査)
WISC-Ⅳは、日本で最も広く使われている子ども向けの知能指数を測る検査で、ギフテッドの可能性を探る際にもよく用いられます。
小児科や心理相談室で受けることができます。
全体のIQ(全検査IQ=FSIQ)だけでなく、「言語理解」「知覚推理」「ワーキングメモリー」「処理速度」という4つの分野に分けたスコアが算出されます。
これにより、「どの分野が得意で、どこに苦手さがあるのか」といった子どもの思考の傾向や特性の偏りが見えてきます。
言葉の説明や図形パズルなど、さまざまな課題を通じて認知の特性を丁寧に見ていきます。
ただし、数値はあくまで目安であり、IQが高ければ必ずしもギフテッドというわけではありません。
QEEG検査
QEEG検査は、脳波を数値として可視化・解析することで、脳の働き方を調べる検査で、「定量的脳波検査」と呼ばれることもあります。
脳のどの部分がどんなタイミングで強く反応しているかを測定し、他の脳波データと比較しながら、その子どもならではの脳の特徴を読み取っていきます。
また、発達障がいとの違いを見極める参考情報として用いられる場合も。
しかし、QEEG検査だけでギフテッドや発達障がいを確実に判別できるわけではなく、脳波に「似たような傾向が見られる」という段階までの検査になります。
今後、研究が進むことで、より高い精度での判別が可能になることが期待されています。
その他の評価方法(面談・行動観察etc)
検査だけでギフテッドかどうかを判断することは難しく、日常の行動や反応を専門家が丁寧に観察することも重要です。
例えば、学校の授業に集中できない、独自の視点で質問を繰り返す、想像力が非常に豊か…といった様子は、評価のヒントになります。
必要に応じて、教育センターや心理相談、学校と連携しながら、多角的に子どもを見ていくことが大切です。
発達障害との違い

よく保護者の方が不安になっているのが、発達障害なのかどうか。
ここでは、ギフテッドと発達障害の類似点と違いを明確にしていきます。
発達障害との類似点(混同されやすい理由)
ギフテッドと発達障がいの子どもには、以下のような共通点が見られます。
共通する特徴の例:
- 興味のあることへの集中力が非常に高い
- 感覚が鋭く、音や光などに敏感
- 論理的思考力が高く、深く考える傾向がある
- 完璧主義で細部に強くこだわる
- 強い探究心があり、自分でどんどん学びを進める
このような特徴が、ADHDの衝動性やASDのこだわりと似ているため、見た目だけでは区別が難しいことがあります。
例えば、授業中にじっとしていられなかったり、先生に質問を繰り返したり、周囲を気にせず熱中してしまったりする様子は、発達障がいの特性と重なって見える場合があります。
発達障害との違い
ギフテッドと発達障害には、いくつかの違いがあります。
例えば、ギフテッドの子どもは、チームの中で自然とリーダー役になることもありますが、発達障害の子どもは集団行動が苦手なことも少なくありません。
また、どちらも集中力は高いですが、ギフテッドは自分で切り替えができるのに対し、発達障がいでは集中が止まらず抜け出せないこともよくあります。
興味の向け方も異なりがあり、ギフテッドは好奇心のアンテナがいくつも立っているようなタイプで、いろんなことに関心を向けます。
一方で発達障がいは、ひとつの道を掘り下げていく“掘削機”タイプで、特定の分野に深くのめりこむ傾向があると言われています。
ギフテッドの子どもに見られる悩み
ギフテッドは、記憶力が良かったり感受性が豊かだったりと、良い面が多いため、不自由ないと思うかもしれません。
ですが、ギフテッドの子供だからこそ抱える悩みがあります。
周囲とのズレによる孤独感・疎外感
ギフテッドの子どもは、同年代との感覚の違いに戸惑い、学校生活の中で孤独を感じやすくなります。
授業内容が簡単すぎて退屈に感じたり、満点を取ることで周囲から浮いてしまうのを恐れて、わざと間違えたり、手を挙げずに答えを我慢していたという子もいます。
同級生が幼く感じて会話が続かず、「ここに自分の居場所はない」と感じてしまう。
友達に合わせようとして口調を変えたり、話題を選んだり、気づけばまるでカメレオンのように自分を演じ続けてしまうこともあります。
過度な感受性によるストレス
ギフテッドの子どもは、感覚がとても鋭いことがあります。
教室のざわめきがうるさく感じたり、蛍光灯の光がまぶしくて落ち着かなくなったり。
何気ない一言に傷つき、あとになってもずっと心に残ってしまうことも。
まわりが気にも留めないことに、ひとり過敏に反応してしまう。
そんな自分を「どうして自分だけこんなに気にしてしまうんだろう」と責めてしまうこともあります。
この繊細さは、豊かな感性や想像力の証でもありますが、気づかれにくいため、本人にとっては、疲れやストレスのもとになることもあるのです。
突出した学習能力からくる授業への意欲低下
ギフテッドの子どもは、理解が早く記憶力にも優れているため、学校の授業が簡単すぎて物足りなく感じることがあります。
すでに理解している内容を繰り返されることで、「なぜこの時間が必要なの?」と退屈してしまい、授業への関心が薄れていくこともしばしば。
一見集中していないように見えても、意識が別のところへ向いているだけなこともあります。
学びに対する意欲がないのではなく、突出した学習能力の影響で、興味を引き出す環境や刺激が不足してしまい、学習意欲が低下してしまうのです。
まとめ
ギフテッドの子どもは、才能に気づいて適切な環境で育つことで、大きな力を発揮できる存在です。
一方、発達障害と似た特性を持つことから誤解されることもあり、生きづらさを抱えているケースも少なくありません。
得意なことと苦手なことの差が大きく、子どもがつらい思いをしているような場面があるなら、知能検査やQEEG検査を受けてみるのも一つの選択肢です。
自分自身を知ることは、才能を活かすための第一歩になります。
必要なのは、周囲の理解と少しの工夫。
その子らしい力の伸ばし方を見つけていくことで、あなたの子どもの可能性はもっと自由に広がっていきますよ。
関連するコラム
習い事を検索
-
- (428件)
-
-
-
-
-
-









