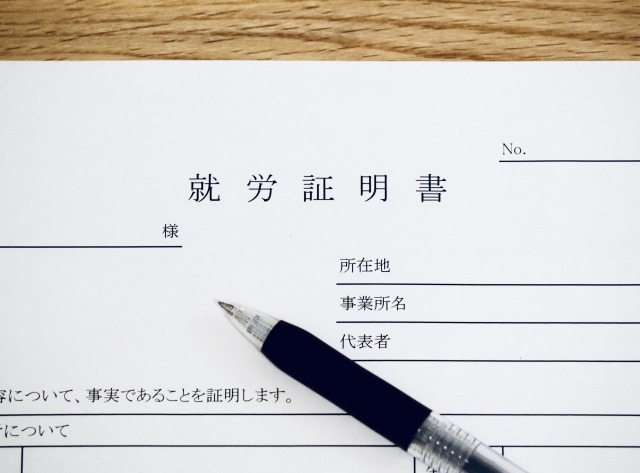認定こども園とは?保育園・幼稚園との違いを徹底解説

子どもの預け先の選択肢に、保育園や幼稚園のほかに「認定こども園」がありますが、他の施設との違いが分からないという方もいるのではないでしょうか。また、認定こども園には4つのタイプがあり、それぞれ特色が異なるため特に複雑です。
この記事では、認定こども園の役割や保育園・幼稚園との違い、4つの種類の特徴やメリット・デメリットについて紹介します。
ぜひ最後までお読みいただき、家庭の状況や教育方針に合った園選びの参考になれば幸いです。
認定こども園の定義と役割
まずは認定こども園はどのような施設なのか、紹介します。
教育と保育を一体的に行う施設
認定こども園は、幼稚園で提供する「教育」と、保育園で提供する「保育」を一体的に行う施設です。従来は幼稚園と保育園の役割は明確に分かれていましたが、共働き家庭が増加している背景から「家庭の就労状況に関わらず、同じ施設を利用したい」という保護者のニーズや、保育園の待機児童増加の背景などから、認定こども園の制度が始まりました。
認定こども園は、0歳児から2歳児の子どもは保育所保育指針に沿った保育を、3歳児以上の子どもには幼稚園教育要領に基づく教育を提供する施設です。保育が必要な子どもには保育園と同じように11時間以上の保育を実施し、教育利用の子どもは幼稚園と同様、日中の4〜5時間程度預かります。「共働きだけど教育面を重視したい」という家庭に人気があります。
内閣府の管轄
2006年10月に認定こども園制度が始まり、2015年4月に「子ども・子育て支援新制度」の施行をきっかけに認定こども園の増加が加速しました。制度を開始した当初は幼稚園を管轄する文部科学省と、保育園を管轄する厚生労働省が連携して対応し、その後は内閣府が調整役となっていました。
しかし、政策が複数の省庁にまたがっていたことで手続きが煩雑だったことや、子ども達への支援を切れ目なく行う目的を達成する必要があることから、2023年4月にこども家庭庁が発足して以降は、認定こども園もこども家庭庁の管轄になっています。
幼稚園・保育園との主な違い

この章では、よく比較される幼稚園や保育園の違いを紹介します。
| 認定こども園 | 保育園 | 幼稚園 | |
| 利用対象者 | 0歳児~2歳児:保育を必要とする家庭の子ども3歳児以降:家庭の状況は問わない | 保育を必要とする家庭の子ども | 家庭の状況は問わない |
| 管轄省庁 | こども家庭庁 | こども家庭庁 | 文部科学省 |
| 保育対象年齢 | 0歳児~5歳児 | 0歳児~5歳児 | 3歳児~5歳児 |
| 職員の資格 | 保育教諭(保育士と幼稚園教諭の両方を持つ職員)※現在は保育士・幼稚園教諭のどちらか一方の資格保持者も可能 | 保育士 | 幼稚園教諭 |
| 保育・教育時間 | 保育標準時間:11時間まで保育短時間:8時間まで教育時間:4~5時間 | 保育標準時間:11時間まで保育短時間:8時間まで | 教育時間:4~5時間程度預かり保育がある園も |
| 申し込み方法 | 保育を必要とする家庭(保育利用):自治体保育の必要性の認定を受けない家庭(教育利用):園に直接 | 自治体 | 園に直接 |
利用対象者(就労の有無)
認可保育所は、保護者の就労や疾病などの「保育を必要とする事由」がある家庭の子どもが利用できる児童福祉施設で、利用するには自治体から「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
一方、認定こども園は3歳以上であれば、幼稚園と同様に保育の必要性がない家庭の子どもも利用できます。もしも途中で保護者が仕事を辞めるなど、家庭の状況が変わったときに、保育園の場合は退園になることもあります。認定こども園は教育利用に切り替える手続きをすれば、同じ園に通えることが大きな違いです。
管轄官庁
前述の通り、認定こども園はもともと内閣府が中心となっていましたが、2023年4月に「こども家庭庁」が発足し、保育園と認定こども園の管轄が一元化されました。
幼稚園は引き続き文部科学省が管轄しています。
保育対象年齢(子どもの年齢)
保育園も認定こども園も、原則として0歳児から5歳児までが対象ですが、施設によって受け入れられる月齢や年齢が違うことがあります。
また、認可保育所の中でも「小規模保育事業」(6人~19名までの少人数の施設)では、原則0歳児から2歳児までの子どもを対象としています。施設形態によって預けられる子どもの年齢が違うので、パンフレットや見学などでよく確認しましょう。
職員の資格
認定こども園の職員は施設のタイプや担当する子どもの年齢によって求められる資格が異なります。
例えば、幼保連携型認定こども園では、職員は「保育教諭」と呼ばれています。教育と保育の両方の専門性を持って子どもに対応するために、原則として保育士資格と幼稚園教諭免許の両方が必要です。ただし、2030年3月までは両方の資格を持っていなくても働ける、経過措置が設けられています。
保育時間・教育時間
保育園の利用時間は、フルタイム就労などを想定した保育標準時間では最長11時間、パートタイム就労などを想定した保育短時間では最長8時間です。申し込み時の保育を必要とする理由や、就労状況に応じて保護者が希望を出し、最終的には自治体が保育時間を決定します。
認定こども園は、利用する認定区分によって時間が異なります。1号認定(教育利用)の子どもは、幼稚園と同様に日中の4〜5時間が基本の教育時間です。2号・3号認定(保育利用)の子どもは、保育園と同様に保育標準時間か保育短時間での利用になります。
申し込み方法
保育園を利用する場合は、保護者の就労状況などを証明する書類とともに、住んでいる自治体の保育担当窓口に申し込み、入園選考(利用調整)を受ける必要があります。
認定こども園の場合は、どの認定区分で利用するかによって窓口が変わります。
保育利用の場合は自治体の窓口に申し込んで利用調整を受け、教育利用の場合は幼稚園と同様、希望する園に直接申し込みを行います。
教育利用の場合も、簡単な入園考査や面談をしたうえで、合否が発表されることがほとんどです。
認定こども園の4つの種類
認定こども園は、成り立ちや特徴によって、大きく4つの種類に分けられます。
幼保連携型
幼保連携型は認定こども園の中で一番多いタイプで、幼稚園と保育所の機能を一体化させている形態です。教育・保育内容は、幼稚園教育要領と保育所保育指針の両方を考慮して作られた「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」にもとづいて行われ、0歳から就学前まで一貫した教育・保育が提供されます。
働く職員は、原則として「幼稚園教諭免許」と「保育士資格」の両方を持つ「保育教諭」であることが求められます。
幼稚園型
幼稚園型は、もともと幼稚園だった施設が、保育所的な機能を追加したタイプです。従来の幼稚園の機能を基本に、保育が必要な子どものために、教育時間終了後や夏休みなどの長期休みの預かり保育を充実させています。
3歳以上の子どもを中心に預かる園が多いですが、園によっては0〜2歳児の受け入れを行っている場合もあります。3歳以上は「幼稚園教育要領」に基づいて教育が行われます。
保育所型
保育所型は、認可保育所であった施設が、幼稚園の機能を追加したタイプです。保育が必要な子どもの保育を基本としながら、保育の必要性がない3歳以上の子どもも受け入れる枠を設けています。
教育内容は「保育所保育指針」に基づきつつ、幼稚園教育要領の内容も考慮しています。
地方裁量型
地方裁量型は、幼稚園・保育所いずれの認可も持たない施設が、市区町村の裁量によって認定こども園としての機能を認められたタイプです。法律上の位置づけは認可外施設ですが、認定こども園として教育・保育を一体的に提供します。
保育所や幼稚園が少ない地域で、既存の施設を活用して地域の保育ニーズに応えるために設けられた種類です。運営の基準などは地域の実情にあわせて条例で定められています。
認定こども園のメリット・デメリット

ここからは、認定こども園を利用するメリットとデメリットを紹介します。
認定こども園を利用するメリット
認定こども園は原則として、保護者の就労状況が変わっても転園する必要がないケースが多いです。家庭状況の変化に関わらず、子どもが慣れ親しんだ環境や友人関係が変わらないことは大きなメリットです。
また、教育利用の子どもと保育利用の子どもが同じ施設で教育を受けるため、多様な家庭環境の子どもたちが交流できること、幼稚園で行うような教育的なカリキュラムを就労しながらでも受けられることもメリットです。
認定こども園の注意点・デメリット
デメリットは、教育利用の子どもと保育利用の子どもで、園での過ごし方や生活リズムが異なることです。教育利用の子どもは午後2時頃に家に帰りますが、保育利用の子どもは夕方まで園で過ごします。教育利用の子どもが先に帰ることで「友達が帰ってしまって寂しい」「なんで自分だけ先に帰るの?」など、子どもが戸惑ってしまう可能性もあります。
また、園によって特色が異なる点も注意が必要です。特に幼稚園から認定こども園に移行した園は、教育カリキュラムや保護者参加の行事が充実している傾向があります。教育熱心な家庭にはメリットですが、共働きの家庭にとっては、平日の行事参加や保護者会の活動などが負担になるかもしれません。逆に保育園から認定こども園に移行した場合、長時間保育や乳児保育には慣れていますが、教育面での特色が薄いこともあります。園見学でカリキュラムや行事については確認し、入園後のギャップが大きくならないように気をつけましょう。
まとめ
認定こども園は、保育と教育の機能を併せ持つ施設です。3歳児以降は家庭の状況を問わずに通園できること、保護者が共働きでも教育的なカリキュラムを受けられることが大きなメリットです。
一方で、認定によって教育・保育時間が大きく異なること、園によっては平日の行事が多くて仕事の調整が必要になる可能性もあります。園の特徴の違いを理解したうえで「家庭に合っているのか」を判断し、子どもに合った園を選びましょう。
関連するコラム
習い事を検索
-
- (428件)
-
-
-
-
-
-