【中学生向け】タブレット学習教材10選!成績を伸ばす選び方とメリットを解説

中学生は部活などで忙しく、勉強が難しい時期です。塾は送迎や費用が負担になるし、通信教育は教材が溜まりがち、そんな悩みを持つ家庭に「タブレット学習」が注目されています。タブレット教材は多くの種類が豊富なので「子どもにあったサービスを知りたい」と考える人も多いのではないでしょうか。
この記事では、中学生向けタブレット学習教材のおすすめ10選、メリット・デメリット、後悔しない選び方のポイントまで解説します。ぜひ最後までお読みください。
中学生向けタブレット学習教材おすすめ10選
まずは、中学生向けタブレット学習教材を10個紹介します。
1.進研ゼミ中学講座
| 料金 | 中一講座 ハイブリットスタイル(タブレット学習中心)12か月一括払いの場合 1か月あたり6,990円(税込)専用タブレット無料(条件あり) |
| コース | ・スタンダード・ハイレベル |
| 対応教科 | 9教科 |
| 教科書準拠 | ◯ |
| 特徴 | ・紙のテキストとの併用・オンラインライブ型授業・自動で個別学習プラン作成 |
| URL | https://chu.benesse.co.jp/ |
進研ゼミ中学講座は、タブレット学習と紙のテキストを併用して学習を進める教材です。タブレット学習では、AIが自動で個別学習プランを作成し、子どもの得意・苦手を分析して問題を出題してくれます。
オンラインライブ型授業も行っており、授業中に講師に直接質問できるほか、チャットの質問対応も充実していることも特徴です。
2.Z会の通信教育(中学生向けコース)
| 料金 | 中1・5教科セット・英語はオンラインスピーキングなし・12か月一括払いの場合月額9,470円から(税込)専用タブレットのほか、iPadでも受講可 |
| コース | 英語は3種類のコースあり・中学英語・中学英語+オンラインスピーキング・Asteria英語 |
| 対応教科 | 5教科・9教科 |
| 教科書準拠 | ◯ |
| 特徴 | ・応用力が身につく質の高いカリキュラム・中学3年分の範囲を公開・外国人講師とのオンラインスピーキング・調査書(内申)対策あり |
| URL | https://www.zkai.co.jp/jr/ |
難関高校の受験を視野に入れている中学生におすすめです。長年の受験指導で培われた質の高いオリジナル問題が特徴です。特に、添削指導の質の高さには定評があり、的確なアドバイスがもらえると好評です。
月1~2回、外国人講師とのオンラインスピーキングに対応する英語コース、調査書(内申)対策など、豊富な独自カリキュラムが設定されています。
3.スマイルゼミ
| 料金 | 中学1年生・標準クラス・12か月一括払いの場合1か月あたり 8,580円(税込)専用タブレット代 10,978円(税込) |
| コース | ・標準クラス・特進クラス・英語プレミアム |
| 対応教科 | 9教科 |
| 教科書準拠 | ◯ |
| 特徴 | ・タブレットのみで学習・記録が完結・1講座約15分で取り組める・お試し期間・タブレット返却で全額返金 |
| URL | https://smile-zemi.jp/chugaku/ |
スマイルゼミは、専用タブレット1台で学習が完結します。タブレットを起動すると、その日の学習が自動で表示され、紙のテキストなどの副教材がつかない点も人気です。
2週間のお試し期間が設定されており、無料で入会後の教材をすべて試せます。期間内にタブレットを返却することが条件ですが、教材の分かりやすさや機器の使いやすさを事前に試せるので安心です。
4.スタディサプリ(中学講座)
| 料金 | 12か月一括払い・クレジットカード決済の場合1か月あたり2,178円(税込) |
| コース | ベーシックコースのみ |
| 対応教科 | 9教科 |
| 教科書準拠 | △(一部対応なし・共通版を選択可能) |
| 特徴 | ・学年が上がっても定額料金で利用可能・専用端末の準備が不要・ベーシックコースの機能を14日間無料体験 |
| URL | https://studysapuri.jp/course/junior/ |
スタディサプリは月額2,178円で、小学1年から高校3年までの全教科・全学年の授業動画が見放題。小学校の復習や、高校の先取り学習もできます。
要点をおさえた1本5分程度の授業動画もあり、短時間で効率的に学習が進められます。
5.東進オンライン学校 中学部
| 料金 | 標準講座・12か月一括払いの場合 3,278円(税込) |
| コース | なし |
| 対応教科 | 5教科 |
| 教科書準拠 | △(一部対応なし) |
| 特徴 | ・東進の実力講師陣の授業を視聴できる・中学校3年間の範囲を受講可能・10日間のお試し入会あり |
| URL | https://www.toshin-online.com/chugaku/chu_index.php |
東進オンライン学校は、大学受験予備校の東進ハイスクールが提供しており、一流講師陣による授業を視聴できます。難しい概念を模型やアニメーションで解説するため、楽しみながら学習できることが大きな特徴です。
中学校3年間の全範囲を受講でき、テストで理解度を確認しながら学習を進められます。「質の高い講師の授業を安価に受けたい」という場合におすすめです。
6.すらら
| 料金 | ・入会金:7,700円~11,000円(税込)・会費(1か月あたり・税込)小中コース・4か月継続割 3教科8,228円・5教科10,428円 |
| コース | ・小中コース(3教科・5教科)・中高コース(3教科・6教科)・小中高コース(3教科・6教科) |
| 対応教科 | 3教科(国語・数学・英語)5教科(国語・数学・英語・理科・社会)6教科(5教科+情報) |
| 教科書準拠 | △(学習指導要領には対応) |
| 特徴 | ・無学年式のオンライン教材・不登校・発達障がいの子へのサポートなど様々なニーズに対応・手持ちのパソコンやタブレットでOK |
| URL | https://surala.jp/ |
発達障がいや不登校など、個別の学習ニーズに対応できると注目されているのが、すららです。無学年学習のため、学年に関係なく、さかのぼって学習をやり直せます。
対話型のレクチャー機能が特徴で、キャラクターが質問を投げかけながら講義が進むため、集中力を保てます。また「すららコーチ」と呼ばれるサポーターが、子どもの特性に合わせて学習設計や見守りのアドバイスを提案してくれるので、保護者の負担が少ないこともポイントです。
7.デキタス
| 料金 | 中学生コース 月額5,280円(税込)全学年コース(小学1年~中学3年) 月額6,050円(税込) |
| コース | 学習したい範囲に応じて小学生コース・中学生コース・全学年コースを選択 |
| 対応教科 | 中学生コース・全学年コース:5教科+英語検定 |
| 教科書準拠 | ◯ |
| 特徴 | ・城南進研グループの講師が監修・アニメのような世界観のポップなキャラクター・授業動画は1動画5分以内 |
| URL | https://dekitus.johnan.jp/index.php |
デキタスは、城南進研グループの講師が監修したタブレット学習教材です。教科書の内容を確実に理解し、基礎基本を身につけたい中学生に適しています。
1回の学習は5分程度の短い動画と、確認問題で構成されています。授業はポップなアニメーションとキャラクター解説で進み、勉強に苦手意識がある子どもにおすすめです。
8.そら塾
| 料金 | 週1回・1科目・80分 月額5,800円(税込)から |
| コース | ・小学生コース・中学生コース・高校生コース |
| 対応教科 | 5教科 |
| 教科書準拠 | ◯ |
| 特徴 | ・オンラインで個別指導が受けられる・オンライン自習室を提供・首都圏有名大学在籍(卒業)の講師が中心・担当講師と合わない場合は変更可能 |
| URL | https://www.sorajuku.jp/ |
そら塾は、東証上場のスプリックスが運営するオンライン個別指導塾です。タブレットなどを使い、先生が隣にいるような感覚で対話しながら学べます。
個別指導にも関わらず、月額5,800円からという低価格を実現しており、教科書準拠のオリジナル教材やオンライン自習室など、成績アップのための仕組みも充実しています。
9.学びAID
| 料金 | 無料 / 月額1,650円(税込)から |
| コース | ・学びエイド(無料会員)・学びエイドfor Premium |
| 対応教科 | 中学生、高校生で習う全範囲の解説・共通テスト・国公立対策・落語 |
| 教科書準拠 | 記載なし |
| 特徴 | ・無料会員あり・1動画5分程度、単元ごとに分類・プレミアム会員はテキストあり |
| URL | https://www.manabi-aid.jp/ |
学びAIDは、大手予備校のトップ講師などの6万本以上の授業動画が、無料会員は毎日3コマまで、有料会員は見放題のサービスです。
授業動画は1本あたり5分程度と短く、単元ごとに細かく分類されています。学校の授業でわからなかった部分だけを、電子辞書のようにピンポイントで探し、すぐに復習することが可能です。
10.eboard(イーボード)
| 料金 | 無料 |
| コース | なし |
| 対応教科 | 5教科 |
| 教科書準拠 | 記載なし |
| 特徴 | ・家庭での利用は完全無料・講義は平均7~8分で、講師の顔が見えずに内容に集中できる・発達障がいや特性に配慮した、シンプルな画面構成 |
| URL | https://info.eboard.jp/ |
eboardは、NPO法人が運営する無料のデジタル学習教材です。さまざまな環境で過ごす、すべての子どもに学習機会を提供することを目的としています。
基礎的な内容を学べるので、まずはタブレット学習を試してみたい人に、特におすすめです。
タブレット学習を使用するメリット

タブレット学習は時間や場所にとらわれずに学習を進められるほかにも、さまざまなメリットがあります。今回は2つ紹介します。
苦手克服や定期テスト対策
タブレット教材には、個人の学習データが記録・AIなどで分析されるものもあります。特に苦手克服や定期テスト対策に有効です。一人ひとりの理解度に合わせて問題を出題したり、間違えた問題などを、忘れた頃に出題する機能などは、知識の定着につながります。
教科書や問題集のどこから手をつければよいか分からない子どもでも、タブレットの指示に従うことで学習を進められることが、大きなメリットです。
視覚的・体験的な学習(動画・リスニングなど)
動画や音声を活用することで、視覚的・体験的な学習が可能です。
例えば英語ではネイティブの発音を繰り返し聞けるリスニング機能、数学では視覚から学べるアニメーションなどを用いることで、効率よく学べます。知識の丸暗記ではなく「なぜそうなるのか」という本質的な理解を進められるので、おすすめです。
タブレット学習のデメリット
ここからはタブレット学習のデメリットを2つ紹介します。
自宅学習により集中維持が難しい
タブレット端末は、Wi-Fiに接続すればSNSや動画視聴、ゲームアプリなどが利用できてしまいます。勉強を始めたはずが、いつの間にか関係のない動画を見ていた、というケースは少なくありません。
学習専用タブレットやペアレンタルコントロール設定を利用し、家庭内でもタブレットの取り扱いルールを検討してみましょう。
また、自宅ではすぐ近くに漫画やスマホなど様々な誘惑があります。
集中して勉強できるようルールや環境を整えることも、大切になります。
視力の悪化
タブレットの画面からはブルーライトと呼ばれる強い光が発せられており、長時間浴び続けると、目の疲れやドライアイを引き起こす可能性があります。
子どもの目を守るために、次のようなルールを決めておきましょう。
- 画面との距離を適切に保つ
- 1時間に1回は遠くを見て目を休ませる
- ブルーライトカットのフィルムを利用する
失敗しないタブレット教材選びのポイント
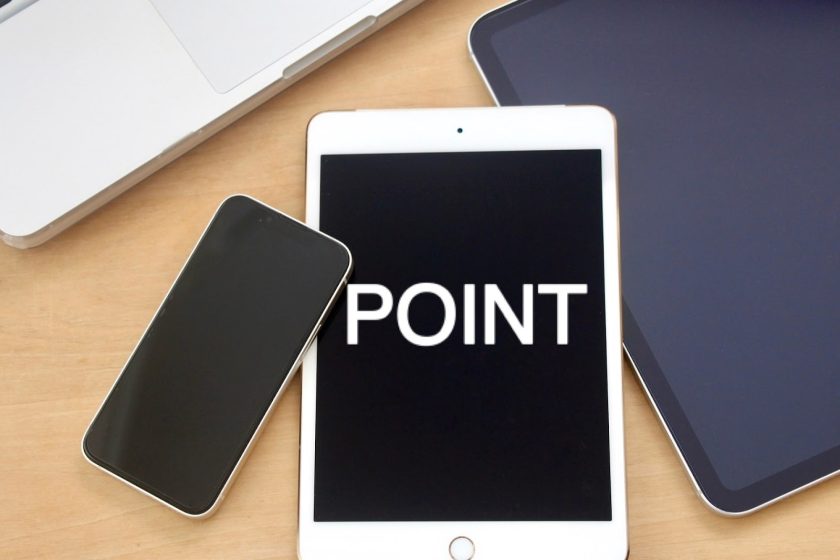
タブレット教材選びでのポイントを、3つ紹介します。
料金体系と追加オプション費用の比較
月額料金が安く見えても、継続受講が前提の価格設定の場合や、入会金やオプションなど、様々な費用が発生するケースが多いです。
あとで「思っていたより費用がかかる」とならないように、事前に次の3点を確認しましょう。
- 入会金や専用タブレット代などの初期費用
- 毎月払いか年間一括払いか
- 基本プランでできる範囲とオプション利用の確認
子どもの学習スタイルに合うコンテンツの確認
どんなに優れた教材でも、子どもが「つまらない」「難しすぎる」と感じれば取り組まなくなります。子どもに合わせて教材を選んであげましょう。例えば勉強に苦手意識がある子どもなら、1回の学習時間が短く、アニメーションやゲーム要素で楽しく学べる教材がおすすめです。難関校を目指す子どもなら、思考力を鍛える応用問題や添削指導が充実した教材を選ぶのがポイントです。
お試し期間がある教材であれば、入会前に子どもに実際に取り組んでみてもらいましょう。
教材に必要なタブレット種類の確認
タブレット教材は、教材会社から提供される専用タブレットで学ぶタイプと、手持ちのタブレットやスマートフォンで学べるタイプがあります。家庭の環境や状況に合わせて選びましょう。
| メリット | デメリット | |
| 専用タブレット | 機能が制限されているので、学習に集中しやすい | タブレット代がかかる(一定期間の継続利用が条件で無料になる場合も) |
| 手持ちのタブレット | 初期費用を抑えられる | インターネット利用の管理(ペアレンタルコントロール)が必要 |
まとめ
中学生向けのタブレット学習は、AIが苦手分野を分析したり、動画で直感的に理解を深められたりする点は、紙の教材にはない魅力があります。一方で、端末設定や取り組みのルール設定など、家庭内での話し合いも必要です。事前に親子でよく検討して、子どもや家庭に合った教材を選びましょう。
関連するコラム
習い事を検索
-
- (428件)
-
-
-
-
-
-









