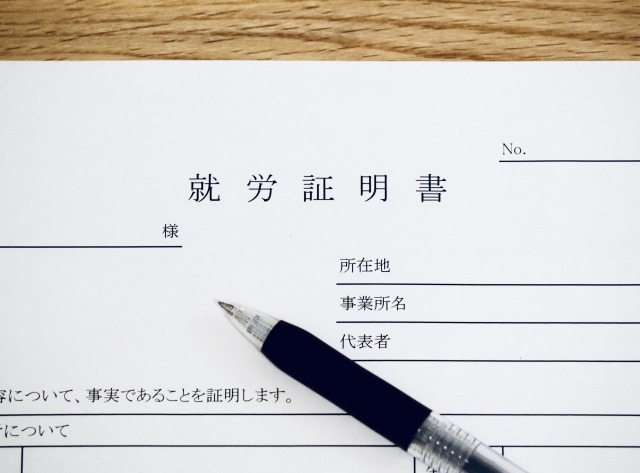「魔の3歳児」のわがままは成長のサイン!知っておくべき原因と対処法

「子どもがわがままばかり言っていて、毎日疲れてしまう」「わがままを言われたときに、どのように対処すれば良いのか分からない」と、お悩みではありませんか?
3歳児のわがままは子どもの心と体が成長しているサインです。誰しもが通る道なので、心配しすぎる必要はありません。しかし、人に迷惑をかけることはやめさせなければいけませんし、子どもの希望を叶えられないときもありますよね。
この記事では、3歳児がわがままを言う原因や対処法、日頃から気をつけたいことを紹介します。ぜひ最後までお読みいただき、親子の関わりのヒントになれば幸いです。
3歳児のわがままはなぜ起こるのか
まずは、3歳児のわがままはなぜ起こるのか、主な理由を3つ紹介します。
自我の発達と自己主張の始まり
一番の理由は、自我がはっきりと発達してくる時期であるためです。「第一次反抗期」とも呼ばれており、脳の前頭前野が発達してくるため「自分で考えて行動したい」「自分でやってみたい」という意欲が高まります。
2歳頃までは、自分の感情を言葉にすることが難しく「イヤ!」と言って泣くことが多いですが、3歳頃は言語発達が進み「おもちゃで遊びたい」などと、言葉で主張できるようになります。親は子どもの要求を理解しやすくなる反面、子どもはより強く自己主張をするため、大人は「わがまま」と感じやすくなります。
感情と言葉のバランスが未熟
先述のとおり、3歳頃は言葉の発達が急激に進み、自分の感情を言葉で伝えられるようになります。
一方で、感情のコントロールや意思決定に関わる、脳の前頭前野の機能が未熟なため、衝動を抑えることがまだ難しい状態です。そのため、理性や我慢がきかず、自分のやりたいことを強く主張し、わがままと認識されやすくなります。
また、言葉の発達が進んでいても、子どもの思う気持ちを全て言語化することは難しいため、上手に伝えられないもどかしさから泣く・叩くなどの行動や、癇癪につながることがあります。
体力や空腹による不快感
大人でも疲れている、睡眠不足、お腹が空いているなどのときに、イライラしてしまう人は多いのではないでしょうか。
子どもも同じで、疲れているときや眠いときなどは不快を感じます。大人であれば「疲れているから休もう」「食事を摂ろう」と自分で対処できますが、子どもはうまく対処できないため、結果としてわがままな言動やぐずりとして表現されます。
わがままが始まった時の対処法

次に、子どものわがままが始まったときの対処法を3つ紹介します。
否定せずに共感する
子どもの気持ちを頭ごなしに否定すると、子どもの感情を抑えつけることになります。まずは子どもの言葉を否定せずに共感して、理解を示しましょう。
例えば、公園で遊んでいるときに「まだ帰りたくない」と言ったときは「まだ帰りたくないんだね」「公園は楽しいから、もっと遊びたいよね」などと、子どもの気持ちを受け止めます。共感を示すことで、子どもは「気持ちを分かってもらえた」と安心し、その後の親の話が子どもに届きやすくなります。
叶えられない要求をされることもあると思いますが、その場合も否定はせずに「気持ちは分かったよ」と、認めることが大切です。オウム返しのようになってしまっても大丈夫なので、子どもの考えを否定しないように気をつけましょう。
気持ちが落ち着くまで見守る
泣いたり怒ったりしているときには、子どもの気持ちが落ち着くまで見守ります。子どもの個性やその時の状況によって異なりますが、次のような方法を試しても良いでしょう。
- 抱っこする
- 身体をさする
- 他のおもちゃなどで気をそらす
- 刺激の少ない場所に移動する
- 子どもの安全を確保し、離れて見守る
激しい癇癪やパニックになっているときには、大人の関わりが刺激になり、さらに気持ちが興奮してしまうこともあります。そのようなときには子どもの安全を確保しながら見守り、少し泣き声が落ち着いてきたときに「抱っこしようか」などと声をかけると切り替えられることがあるので、タイミングを見極めて関わりましょう。
要求が通らない理由を伝える
子どもが落ち着いてきたら、なぜ子どもの要求が通らないのかの理由を伝えます。
先ほどの公園の例では「ごはんを作るのが遅くなって、お腹が空くといけないから、今日は帰ろうね」など、子どもに分かりやすい言葉で、端的に伝えましょう。「すべり台を3回やったら帰ろうね」「帰ってごはんを食べたら、積み木で一緒に遊ぼうか」などの代替案を提示するのも、子どもは納得しやすいのでおすすめです。
わがままを減らすための日頃の関わり方
子どものわがままを減らすために、日頃からできる関わり方を紹介します。
子どもに選択肢を与えて自分で決めさせる
「自分で決めたい」という自我の要求を満たすために、いくつか選択肢を提示して、子どもに自分で選んでもらうと満足感を感じやすいです。自分で選ぶ経験は、子どもの自主性を育みます。
選択肢が多いと子どもが混乱してしまうことがあるので、2択程度に絞って提示することがおすすめです。例えば「黄色の洋服と緑の洋服、どっちを着る?」「朝ごはんはパンにする?ごはんにする?」など、親も無理せず対応できる範囲で選択肢を与えられると良いでしょう。
できたことや我慢できたことを褒める
子どもが約束を守ったときや、我慢したときには、ぜひ褒めてあげてください。行動心理学では「正の強化」と呼ばれ、褒められた行動が定着しやすくなる効果が期待できます。
「声をかけたらすぐに片付け始めてくれたね!ママ(パパ)は嬉しいよ」「もっと遊びたかったのに、時間を守ってくれてありがとう。また明日、公園に来ようね」など、具体的な行動を挙げて、どのように良かったのかを褒めてあげましょう。どうしてもやめてほしい行動に目が向きがちですが、良い行動に注目すると「次もがんばろう」と、子どもも意欲的になります。
生活リズムを整えてストレスを減らす
体力や空腹の不快感を減らすために、毎日の生活リズムを整えることも大切です。次のような点に気をつけましょう。
- 決まった時間に起床・食事・就寝する
- 日中はなるべく身体を動かして遊ぶ
- 疲れているときや体調が良くないときには無理をしない
生活リズムを整えることで体内時計が整い、ストレス耐性が高まります。もし、保育園や幼稚園に通っていれば、休日も園の生活リズムに合わせると、より安定した生活を送りやすくなります。外出などで難しいこともあるかもしれませんが、できる範囲で生活リズムを整えて過ごすことがおすすめです。
また、子どもだけではなく、親も食事や睡眠がしっかりとれるように気をつけていきましょう。
親のイライラを和らげるために

子どもへの関わり方だけでなく、親のマインドコントロールも同じくらい大切です。ここからは、親のイライラを和らげるための考え方を紹介します。
完璧主義をやめる
「この時間までに、これを終わらせなくちゃ」「子どもを良い子に育てなければ」など、完璧に育児をしなければならないと思うことで、余裕がなくなります。子どもは大人の思い通りに動かない・育たないものです。怪我につながることや、他者に悪影響があれば止めなければいけませんが、危険がなければ見守ってみることも大切です。例えば、帰りは遅くなるけど10分程度遊ばせてあげるなど「こうしなければいけない」という考えから「まあいいか」という考えに変えて、心のゆとりを持って対応しましょう。食事は市販品を活用する、掃除は少し手抜きするなど、家事の工夫をすることも良いですね。
気持ちに余裕を持つためには、親自身が元気に笑顔でいることが大切です。生活リズムを整え、好きなことに没頭する時間を作るなど、親が元気でいられるように過ごしましょう。
予めルールや約束事を決めておく
家庭内での対応の差を防ぐため(一貫性を持って対応するため)にも、事前に家族で話し合ってルールを決めておくのがおすすめです。「ママはダメだけど、パパは良い」など、対応がぶれることで、子どもが混乱してしまいます。混乱からわがままや癇癪につながることもあるので、対応の線引きは家庭内で揃えておくようにしましょう。
3歳頃は少しずつルールやマナーが分かるようになる時期でもあります。しっかりとルールを決めることで、子どもも習慣化できるので、繰り返し伝えましょう。
また、子どもが遊び始める前には、ルールや約束事をおさらいすると、子どもも心の準備ができます。例えば「時計の長い針が9にきたら帰るよ」「公園の外は車や自転車が走っていて危ないから、門から出ないで遊んでね」など、実際に時計を指さしたり、公園の門に行ったりしながら、子どもに伝えると効果的です。理解しやすいように、短い文章で伝えましょう。
わがままは成長のサインという認識をもつ(一過性という認識)
子どものわがままは成長の過程で起こっているものであり、一過性のものです。わがままを「成長のサイン」として捉え直すことで、受け止め方が大きく変わるでしょう。言うことを聞かないのは「自分の意志が育っている証拠」、反抗するのは「自己主張ができるようになった証」と前向きに解釈できます。
大変な時期は一時的なもので「いつかは終わるもの」と理解することで、子どものわがままに大らかな気持ちで向き合えるようになります。
まとめ
3歳児のわがままは「自分でやりたい!」という気持ちを、上手にコントロールできないために起こります。成長の過程で誰もが通る道ですが、この時期の親子の関わりが、子どもの自己肯定感につながります。子どもの気持ちを受け止めつつ、危険なことや人に迷惑を掛けることは、毅然とした態度で対応することが大切です。
また、子どもが笑顔でいるためには、親自身のストレスケアも大切です。休息をしっかりとり、時には好きなことに没頭する時間を作って、ストレスを溜めないようにしましょう。
関連するコラム
習い事を検索
-
- (428件)
-
-
-
-
-
-